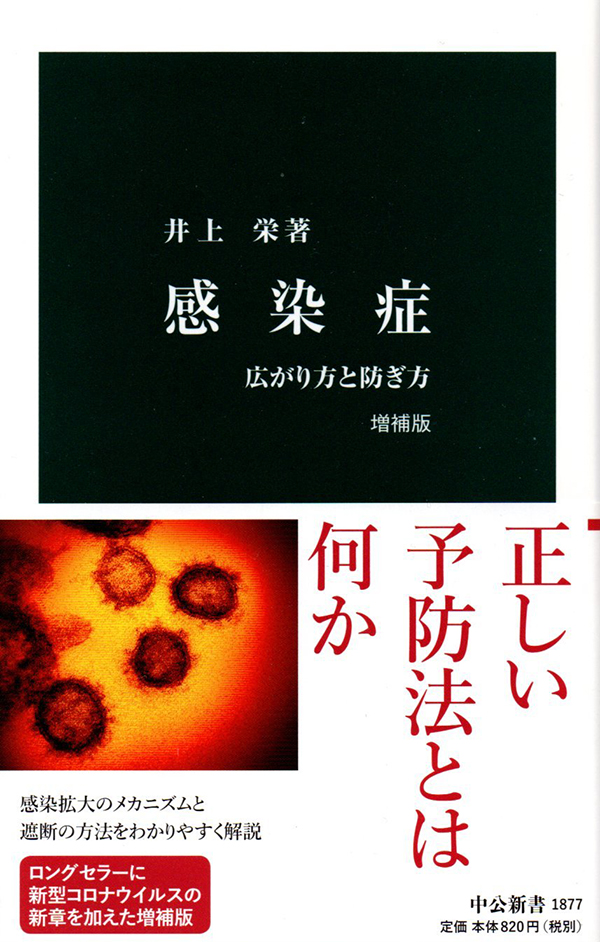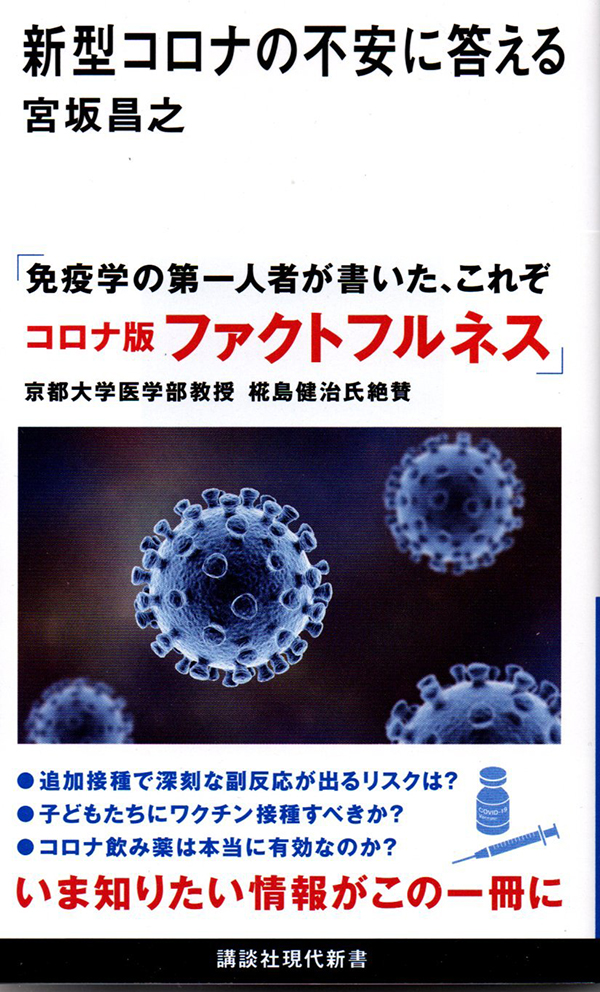パンデミックからはや3年─“ウィズコロナの知識武装”に効く2冊
新型コロナウイルス感染症が2020年1月にパンデミックをおこして、間もなく3年が経とうとしている。
この3年を通じて、コロナはすっかり身近なものになったが、我々にとってあいかわらず未知で不気味なものであるということに変わりはない。
コロナを正しく知り、正しく怖がるための処方箋を、『感染症―広がり方と防ぎ方』『新型コロナの不安に答える』の2冊に探ってみよう。
『感染症―広がり方と防ぎ方』に探る、日本人が感染症に強い理由
ウイルスを正しく知ることは重要である
まず最初にこの本を読もうと思ったのは、コロナ渦前に書かれた本だからである。
コロナウイルスの襲来によって、今というときを生きている我々は、感染症についての考え方がガラリと変わった。だが、人類と感染症との付きあいは、有史以前からのものである。コロナはいつ収束するのか、ワクチンは有効なのか、といった直近の状況に対応する答えを探る前に、これまで人類が積み重ねてきた感染症についての基本的な知識を知りたいと思ったのだ。
2022年4月25日に刊行されたこの本の『増補版』では、新章にあたる「新型コロナウイルスが広がりにくい社会」が加えられていて、コロナ前に書かれた記述と今の概念とに矛盾がなさそうなのも望ましい。例えばこれが、原子力発電について書かれた書物で、3.11の福島原発事故以前と以後に書かれた本とでは、こうはいかないだろう。
国立感染症研究所の感染症情報センター長をつとめた経歴のある井上氏は、ウイルスの基本的な性格について、こう説明している。引用しよう。
ウイルスは、遺伝子核酸(RNAかまたはDNAのどちらか)と、それを囲む蛋白質からなる単純な構造体で、細胞でない生物である。細胞である細菌の10分の1以下の大きさであり、培地では増殖せず、自己を複製するときには特定の細胞に肺って、その代謝系を利用して殖える。
ということで、細胞の外にいるウイルスは、生物とは呼べない無生物として挙動する。従って、ウイルスが生物と同じように子孫をたくさん残して地球上に生存し続けるためには、感染先の宿主といい関係を築かねばならない。
強烈な毒を発して宿主を殺せば、ウイルスは宿主とともに死ぬことになる。おそらく、過去には宿主がすぐに死ぬような強毒性のウイルスも地球上の歴史のなかで多く登場したと思うが、そうしたウイルスは宿主と共倒れになって、ダーウィンの自然淘汰の説の通り、絶滅していったと思われる。
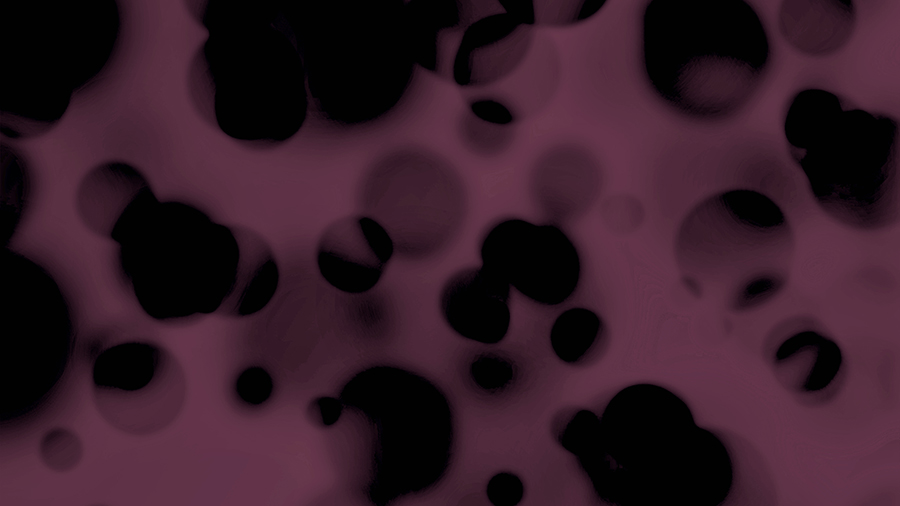
一方、宿主をすぐに死なせず、重症にさせ、寝込ませる程度に毒性を抑えたウイルスは、人間に感染した場合、はげしい咳による飛沫や、乾燥して空気中をただようエアロゾルに乗って、次の感染先の宿主への移動手段を持つことになる。
それ以上に有利な生存戦略をとったのが、宿主を寝込ませない、さらに弱毒化したウイルスだ。潜伏性があるので宿主は感染したことに気づかず、感染後も動きまわって他の宿主に住む場所を提供してくれるのである。新型コロナウイルスは、その典型例だ。
人間とウイルスとの関係で言えば、人間の文明が未発達で、ひとつの場所に多数の人が寄り添って居住する環境が多かった時代は、宿主を重症にさせるウイルスも幅をきかせていた。ところが、グローバル化による人やモノの大移動が可能になった現代においては、弱毒化という戦略をとったウイルスが地球上にはびこることになる。
おもしろかったのは本書の冒頭の、2003年に流行したSARS(重症急性呼吸器症候群)についての考察である。
この年の2月21日、香港のMホテル9階に泊まって感染した客が、ベトナム、カナダ、アイルランド、米国、シンガポールへ移動して、8000人余の患者が報告されるほどの世界的な流行を招いた。そのとき、宿泊客のなかに日本人もいたが、日本人の患者はゼロだった。なぜ日本人旅行者だけが、ウイルスに感染しなかったのか? 本書の旧版が出版されたのは2006年12月だが、その疑問に触発されての出版だったそうだ。
新型コロナウイルスでも、海外に比べて日本では感染者や死者が少なく、「ファクターX」なる要因がありそうだと指摘されたが、大いに参考になりそうな考察だ。
“ファクターX”なる要因は、日本人の生活様式や発音からも考え得る!?
SARSは、人間の肺や腸管で増殖するため、咳などによる飛沫感染だけでなく、糞便にふくまれるウイルスによる伝播がおこった可能性があるという。
トイレのドアノブについたウイルスが別の人の手に移り、握手やお札、硬貨を数えることで、また別の人の手に移る。それから靴に糞便がついて、ウイルスが運ばれ、ホテルの部屋で乾いてホコリとなって舞い上がり、それを吸い込んで感染する。そうした可能性を挙げつつ、井上氏は日本人が感染しなかった理由を次のように考える。
いっぽう日本人旅行者は、握手のかわりにお辞儀をすることが多いので、手の接触が少ない。ホテルの部屋に入ったら土足をぬぐ。外国のホテルにはスリッパはないのだが、日本人ではそれを持参する人もいる。手を洗い、風呂にも入る。
日本人は食事に箸を使う。寿司、おむすびを除けば、手づかみで食べることは少ない。たとえウイルスが手についていても、箸を使えば口に入りにくいことになる。さらに日本食レストランではお手ふきが出て、それを使っただろう。
というのが、日本人旅行者がウイルスを自国に持ち帰らなかった理由だというが、非常に説得力がある。
「感染症のさまざまな伝播経路において、病原体がうつりにくい条件が生活のなかに組み込まれて存在している国は日本だけである」と語る井上氏は、日本語の発音にも着目して、これを分析している。
英語と中国語には有気音がある。有気音とは、p・t・k(中国語ではさらにq・ch・c)の破裂音のあとに母音が来ると、息がはげしく吐き出されることをいう。口の前にハンカチをたらしておくと、それがめくれ上がることでわかる。息を出すときウイルスをふくむ飛沫もとびだすだろう。
いっぽう日本語では、p・t・kは息を出さない無気音として発音される。しかも日本語ではp音はあまり使われていない。ハ行音は、奈良時代p音だったのがのちf音に変わり、いまはh音になっている。現在、パ行音は外来語か擬声語・擬態語に使われるだけである。
そのため、日本語で会話する日本人は飛沫感染をおこしにくいというのだが、井上氏はこの仮説を実証するため、風圧実験を行っている。
村上春樹の『ノルウェイの森』のなかの文章を日本語原文と英語、中国語の翻訳とをそれぞれネイティブ話者に音読させ、口から飛び出す風圧を測定するのである。215ページに掲載された、英語話者と日本語話者の風圧グラフを見ると、確かに英語のほうが日本語より高い風圧で言葉を発していることがわかる。
157ページには、マスクによる咳風速の減弱度の測定結果も示されている。このとき、マスクは70円の16層ガーゼのマスクと、20円の3層の不織布マスク、5円の2層紙マスクの3種類を比較しているが、どのマスクでも咳による風速は10分の1に減弱したという(ゆえに「同じ効果ならば、いちばん安くて、かつ患者の呼吸に負担がかからない5円のマスクがよい」ということになる)。
まるで推理によって犯人を当て、その犯行のトリックを暴く名探偵のような手さばきである。
本書では、近代免疫学の創始者であるジョン・スノウ(1813~1858)がコレラ菌が発見される40年近く前から推理力のみを使ってロンドンでのコレラ感染を収束させた名探偵ぶりも紹介されるが、読み物として非常におもしろい。かつ、感染症についての基礎的な知識を得るのにうってつけの良書だった。
『増補版 感染症 広がり方と防ぎ方』
- 著者:井上栄
- 発行:中公新書
- 定価:820円(税別)
- ボブ的オススメ度:★★★★☆
『新型コロナの不安に答える』では、最新の科学データで「フェイク」を論破!
コロナワクチン開発の歴史をひもとくと50年以上も遡る!?
続いて読んだのが本書、『新型コロナの不安に答える』。著者の宮坂氏は、免疫学者として50年以上にわたって基礎ならびに臨床研究を続けてきた権威である。本書は、そんな宮坂氏の『新型コロナ 7つの謎』(講談社ブルーバックス)、『新型コロナワクチン 本当の「真実」』(講談社現代新書)に続く3冊目の著書で、免疫学や感染症学の最新の知見をもとに新型コロナウイルスやワクチンについて正しい知識を指南している。
当然、デマや陰謀説、フェイクニュースなどが主張する根拠のない説に対する、宮坂氏の批判は手厳しいものになる。
私はいわゆる「嫌ワクチン本」「反ワクチン本」といわれる著作や記事にもできるだけ目を通すようにしていますが、残念ですが、説得力を持つ根拠を提示しているものはほとんどないように思います。その多くは科学的に誤った理解に基づく恣意的な解釈、思い込み、感情的な批判に終始していました。
というわけで、本書では折にふれてそうしたトンデモ説をやり玉に挙げて論破していく。
例えば、「オミクロンは病原性が低いので、自然感染にまかせて集団免疫を獲得すればパンデミックは収束する。オミクロンはかえって社会にとって『福音』となるかもしれない」という説に対する宮坂氏の反論はこうだ。
自然感染によって獲得できる免疫の質は高くないうえに持続時間も短いため、次から次に変異株が登場する状況では集団免疫はいっこうに成立しないからです。一方で制御できない感染爆発によって多くの方が命を落とすでしょう。わずか2年で、全世界で約6000万人が命を落としたという事実を忘れてはいけません。
それから、メッセンジャーRNAワクチン(mRNAワクチン)についても「このワクチンは開発されて1年ぐらいの新しいもの。人への投与はまだ2年ぐらいだ。何年か経ったらとんでもない副反応が出てくるかもしれない。だから怖くて接種を受けられない」との主張には、このワクチンの開発の歴史を丁寧にひもときながら解説している。
宮坂氏によれば、mRNAの操作技術の開発は、1961年にmRNAが発見されて以来、50年以上にわたって続けられてきたのだという。

意外だったのは、当初は感染症のワクチンではなく、がん治療の目的で研究開発が行われていたということ。マウスにmRNAを投与して、生体内でmRNAの産物、すなわちタンパク質を作ることに成功したのが1990年のこと。2001年にはmRNA取り込みによって免疫系の番人である樹状細胞に腫瘍抗原を発現させ、その樹状細胞を投与することによってがん治療を行うという実験的な試みが始まった。
ところが、その間、mRNAを投与すると自然免疫が活性化されて炎症が起きることがわかってきた。これによって暗礁に乗りあげたかに見えたmRNAワクチン技術だが、2008年にこれを解決したのが、故国ハンガリーを追われて米国に亡命して研究を続けていたペンシルベニア大学のカタリン・カリコ博士である(娘のテディベアに所持金を隠して渡米したという逸話は有名)。
カリコ博士は、RNAの構成成分のひとつであるウリジンをシュードウリジンに変えることで自然免疫反応を軽減し、mRNAの生体内翻訳の効率を改善したのである。この業績はmRNAワクチン開発に必須となり、ノーベル賞級の技術として賞賛された。
宮坂氏はこれらの歴史を説明したうえで「新型コロナワクチン自体は、確かに1年ぐらいの開発期間でできています。しかし、その基礎技術の開発は前述のごとく20年にもおよび、mRNAワクチンとしても10年以上の開発の歴史があります」と論を展開する。まことに信用するに値する、説得力のある説明である。
めまぐるしく変わる世の中の動きの中では、最新データの分析が不可欠
ただし、宮坂氏自身、「執筆にあたってはその時点の最新データをもとにしましたが、書籍の性質上、刊行後は情報が徐々に古くなっていきます」と告白している通り、すでに情報が古くなってしまった部分があることは否めない。
例えば、オミクロンに対応する改良型ワクチンの追加接種について「オミクロンは免疫回避方の変異株であるため、開発するのが難しい」という理由で、市場に出回るには時間がかかるとの記述があるが、ファイザー社とモデルナ社のオミクロン対応ワクチンはすでに市場に投入されている。
従来型とBA.1との2価ワクチンが薬事承認されたのは、2022年9月12日のこと。次いで同年10月5日には従来型とBA.4-5との2価ワクチンが薬事承認されている。
本書が刊行されたのが同年の3月30日だから、刊行後半年で情報が古くなってしまっている。新型コロナをめぐる世の中の動きが、それだけめまぐるしく動いているということだろう。
というわけで、本書は刊行した時点で最新のデータをもとに執筆されていることは事実に違いないが、その取り扱いには多少の注意が必要のようだ。
私(内藤)は、コロナがアルファからベータ、ガンマ、そしてデルタへと変異した直後に罹患した。2021年8月10日のことで、日本の感染者数が100万人を超えたピークのころである(2022年11月時点での感染者は342万人)。
3日間続く高熱と味覚障害(口にするものすべてが正露丸風味になる)を経験し、もう2度とこんな目には遭いたくないと思っている。
だが、コロナはオミクロンに姿を変え、いまだ私たちの日常に居座り続けている以上、ヤツらのことをもっとよく知り、知識武装しておくことが必要だ。この2冊はその重要なヒントを与えてくれたと思う。
『新型コロナの不安に答える』
- 著者:宮坂昌之
- 発行:講談社現代新書
- 定価:900円(税別)
- ボブ的オススメ度:★★☆☆☆
よく読まれている記事
よく読まれている記事
特集
介護の基礎知識


介護の悩みを
トータルサポート

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。