ニュース
#最新研究
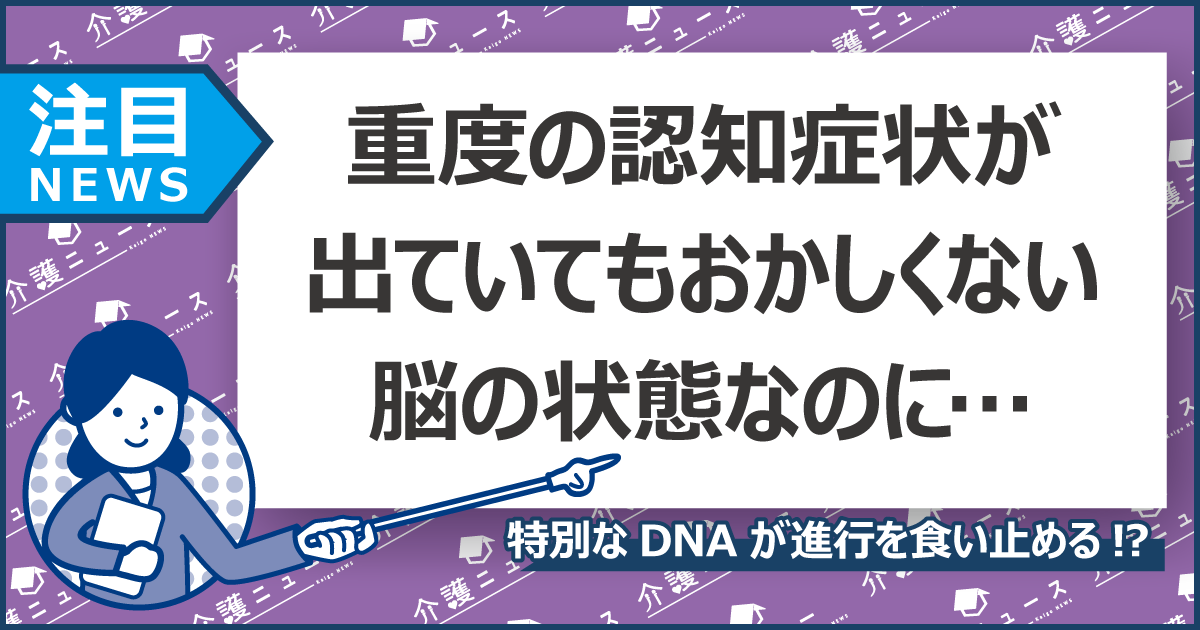
認知症の進行を食い止める遺伝子を発見!?特殊なタンパク質がバリアに
認知症の大きな要因として挙げられるのが、脳内に異常なタンパク質が蓄積することで発症する「アルツハイマー病」。一度発症すると数年で物忘れや妄想などの認知症の症状が現れます。現時点では、完全に治す方法はありません。 今回、そんなアルツハイマー病の進行を大幅に遅らせる可能性のある遺伝子が新たな研究で発見されました。 この研究は、コロンビアのアンティオキア大学医学部の研究グループによって実施され、研究結果は「Nature Medicine」という医学誌に掲載されています。 とあるコロンビア人男性の話 研究グループは、コロンビアに住む約1200人の家族の臨床データと遺伝子データを分析。すると、とある男性の遺伝子からアルツハイマー病の進行を遅らせると思われる遺伝子を発見しました。 その男性の脳を調べると、萎縮した脳内に、「アミロイドプラーク」と呼ばれるタンパク質と「タウ」と呼ばれる別のタンパク質が見つかりました。 これらは通常、重度の認知症を患っている人に見られますが、この男性の認知機能はまだそれほど低下していませんでした。 つまり、この男性は本来なら重度の認知症の症状が出ているはずなのに、何らかの理由でまだ軽症で済んでいたのです。 特殊な遺伝子が発症から守っていた 男性にさまざまな検査をおこなった結果、「リーリン」と呼ばれるタンパク質をコードした遺伝子を持っていることが判明。この特殊な遺伝子が、男性を何十年もの間、認知症の発症から守っていたのです。 また、本来なら早い段階で侵される領域である、記憶に関与する神経細胞がほとんどダメージを負っていないことも明らかになりました。男性の遺伝子の一部が、神経細胞を保護するバリアになっていたのです。 ただ、なぜ「リーリン」をコードした遺伝子が、認知症の発症を長い間抑えられたのかは明らかになっていません。今後この研究がさらに進んでいけば、認知症の発症そのものを防止する治療が可能になるかもしれませんね。 参考:「Resilience to autosomal dominant Alzheimer’s disease in a Reelin-COLBOS heterozygous man」
2023/05/19
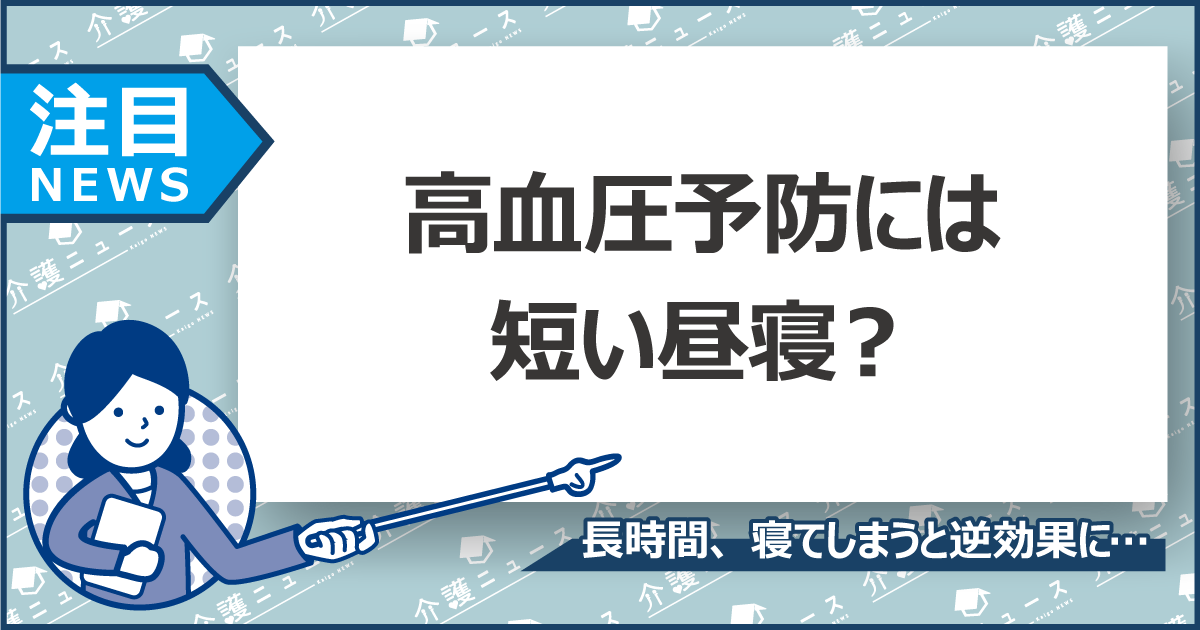
長時間の昼寝で高血圧に!?でも30分未満の昼寝は健康に良い!
新たな研究で、長時間の昼寝をする習慣がある人はそうでない人に比べて、肥満や高血圧のリスクが高いことが示されました。 この研究はアメリカのブリガム・アンド・ウィメンズ病院によっておこなわれ、研究結果は「Obesity」という学術誌に掲載されています。 昼寝の効能 一般的に、短時間の昼寝は身体や脳の疲労を取るのに効果的だと言われています。最近では、15~20分程度の昼寝は「パワーナップ」と呼ばれ、仕事の生産性を高めるために導入している企業もあるほどです。 しかし、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の睡眠・概日リズム障害部門に所属するマルタ・ガローレット氏によると、「昼寝が長時間に及んでいる場合には、悪い影響が現れるリスクが高まる」と言います。 昼寝の時間が長すぎると体内時計が乱れ、望ましい時間に眠ったり起きたりすることが難しくなるのだそうです。 長時間の昼寝をしている人は血圧が高い 今回、研究グループは、スペインなどの地中海地域の住民を対象に調査を実施。生活スタイルと、肥満や認知症などとの関連を調べている研究に参加した3275人の医療データを分析しました。 その結果、昼寝を1日に30分以上する習慣のある人は、そうでない人に比べて肥満かつ血圧が高い傾向にあることが示されたのです。 一方、15~20分程度の短い昼寝をしている人は、まったく昼寝をしない人に比べて血圧が低いこともわかりました。 今回の研究をリードしたガローレット氏は、「昼寝の効果は時間の長さや睡眠の質、1日のリズムなどさまざまな要因によって変わってくる。それらを考慮に入れて昼寝の長さを調整することが大切だ」と指摘しました。 休みの日などは、疲れて1日中ベッドの中にいるという人も少なくありませんが、そのような生活習慣が続けば自律神経が乱れてしまう可能性もあります。健康に過ごすためにも、少し外に出て、太陽の光を浴びるようにすると良いかもしれませんね。 参考:「Longer siestas linked to higher risk of obesity, metabolic syndrome, and high blood pressure」
2023/05/17
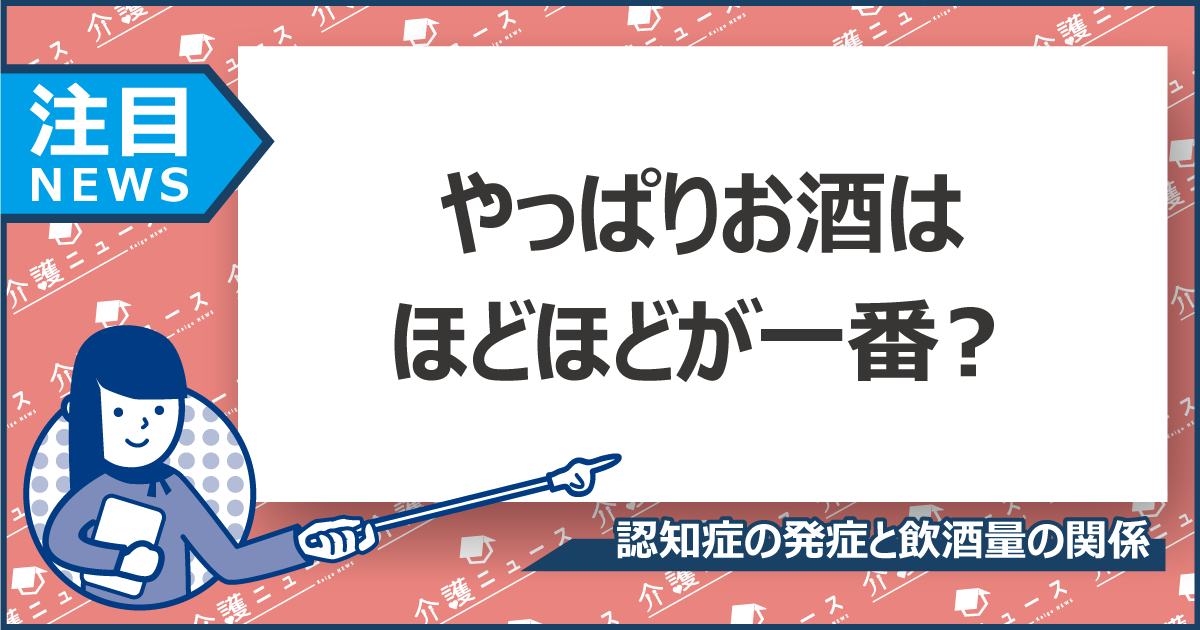
認知症リスクお酒をたくさん飲んでも全く飲まなくても高くなる!?
新たな研究で、お酒を多量に飲む習慣のある人は認知症の発症リスクが高まる可能性が示されました。 この研究は国立がん研究センターによっておこなわれ、研究結果は「Geriatric Psychiatry」という学術誌に掲載されています。 お酒を多量に飲む人は認知症リスクが高まる 今回、研究グループは秋田、長野、沖縄、茨城、高知に住む4万2870人の中高年を対象に調査を実施。調査開始時(1995~1999年)とその5年後に飲酒習慣に関するアンケートをおこないました。 さらに、2016年まで追跡して調査。対象者のうち約11%の人が認知症と診断されたことがわかりました。 その後、研究グループがデータを解析した結果、アルコールを週に300g~450gを飲んでいる人は最もリスクが少ない人に比べて1.13倍、450g以上を飲んでいる人は1.34倍も認知症を発症するリスクが高まることが示されたのです。 一方、最も認知症のリスクが少なかったのは、週に75g未満のアルコールを飲んでいる人であることもわかりました。週に75gのアルコール量を具体的に述べると、ビールでは中瓶(500mL)を3.5本、日本酒では3.5合くらいです。 お酒をまったく飲まない人も認知症のリスクあり? 研究グループが解析を進めていくと、お酒をまったく飲まない人も、週に75g未満のアルコールを飲んでいる人に比べて認知症のリスクが1.29倍高いことが判明しました。 これについて、研究グループは「アルコールを飲まない人の中には、うつ病などの精神疾患や糖尿病などの代謝系疾患にかかって飲酒をやめた人なども含まれている。これらの疾患が認知症リスクとも関連しているために、高いリスクを示した可能性がある」と指摘しました。 大量飲酒は、脳の萎縮や脳卒中の原因になる可能性なども別の研究で示されています。健康に毎日を過ごすために、適度な量で楽しくお酒を飲むようにしたいですね。
2023/05/17
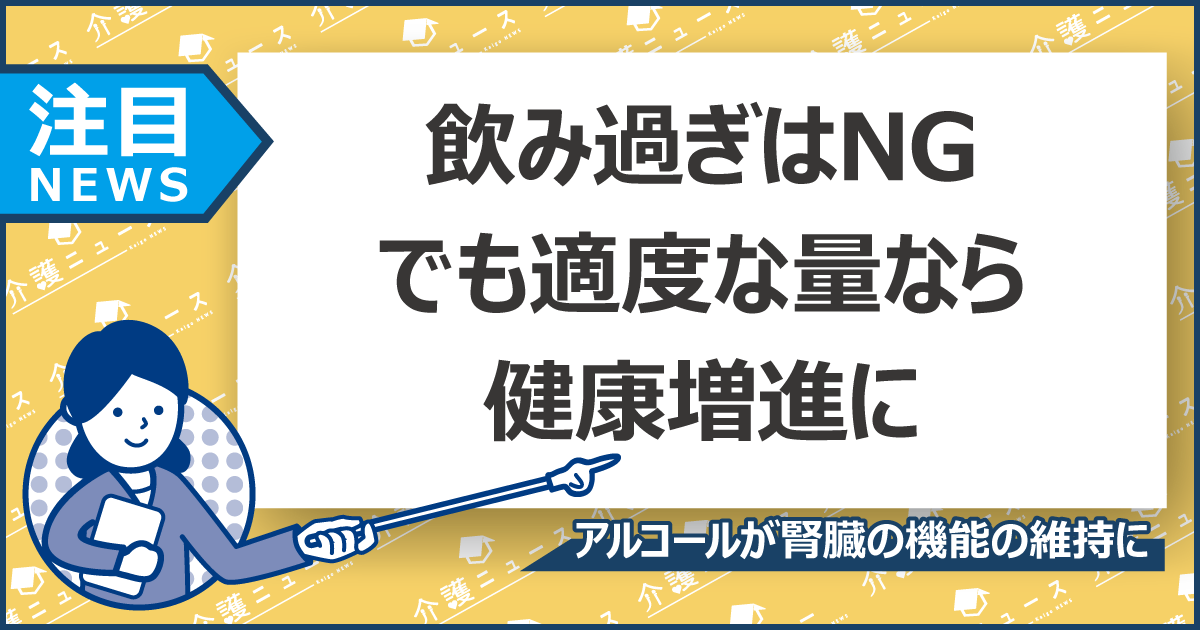
腎臓病予防にお酒!?適度なアルコールが健康維持に。飲み過ぎは注意
新たな研究で、適度にお酒を飲んでいる人は、ほとんどお酒を飲まない人や大量に飲む人に比べて、腎機能低下のリスクが下がる可能性が示されました。 この研究は大阪大学によっておこなわれ、その研究結果は「Nutrients」という学術誌に掲載されています。 慢性腎臓病について ところで、腎臓の機能が低下した状態が続いた場合、どのような経過をたどるのでしょうか? 糖尿病や腎臓病に関するニュースなどを提供している日本医療・健康情報研究所によると、腎臓の機能がかなり低下するまでは自覚症状が現れないことも多いと言います。 腎臓病が進行し、腎臓の働きがかなり悪くなってくると、次第にだるさや頭痛、むくみなどの症状が現れるそうです。遅くともこの段階までに治療を開始しなかった場合は、機能しなくなった腎臓の代わりに血液中の余分な老廃物を人工的に取り除く、透析療法をおこなわなければ命の危険につながることもあります。 日本医療・健康情報研究所は、手遅れにならないように、定期的に検査を受けて腎臓病の早期発見に努め、異常が見つかったらすぐに治療を始めることが重要だとしています。 適度な飲酒は腎機能低下のリスクを下げる 今回、研究グループは全国に住む40~74歳の健診受診者30万4939人の医療データを分析。腎機能の推移を約3年にわたって追跡した結果、1日あたりのアルコール摂取量が日本酒3合以上の男性やほとんどお酒を飲まない男性は、腎機能の低下リスクが高まる可能性が示されたのです。 言い換えると、適度な飲酒習慣(1日あたり、ビールのロング缶1本分もしくは日本酒1合相当)がある男性は、腎機能の低下リスクが下がることがわかりました。 一方、女性では明確な関連性が見つかりませんでした。 今回の結果を受けて、研究グループは「適度な飲酒は腎臓病の予防につながる可能性が示された」と述べています。 よくお酒は「百薬の長」と称されますが、「されど万病のもと」でもあります。お酒の許容量は人によって異なるため、自分の体質に合った量でお酒を楽しむようにすると良いですね。
2023/05/15
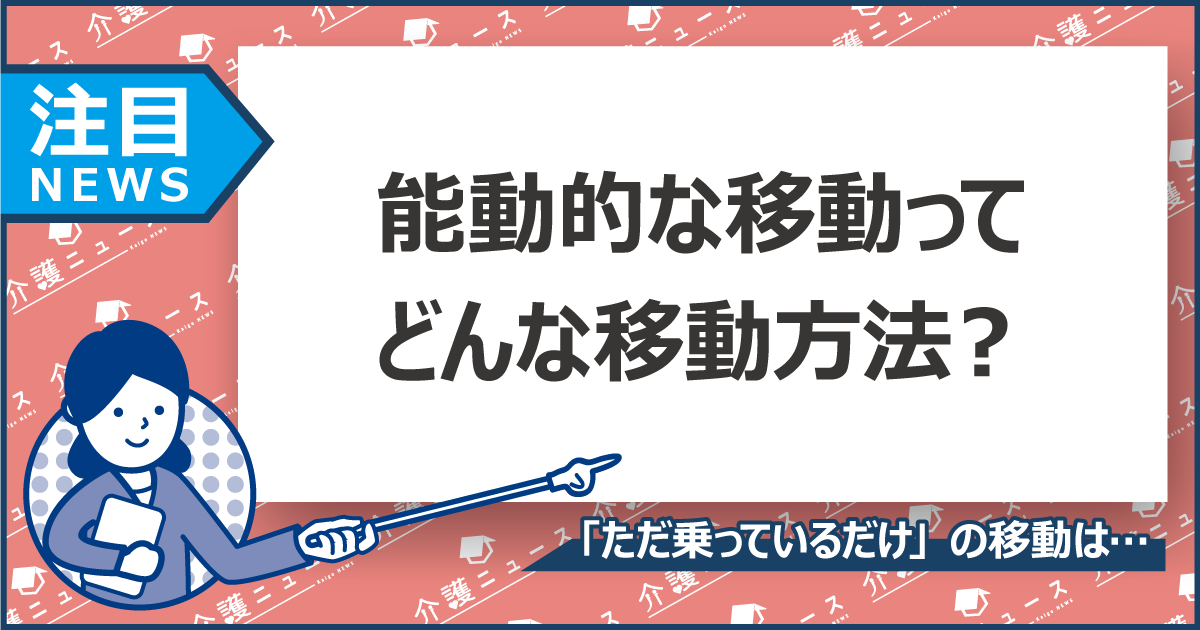
車やタクシー移動ばかりだと介護リスク上昇!?”能動的”な移動が介護予防に
新たな研究で、タクシーなど乗車だけで移動が完結する「受動的」な移動手段を多く用いている高齢者は、徒歩や自転車などの「能動的」な移動手段を多く用いている人に比べて、「手段的日常生活動作(IADL)」が低下しやすい可能性が示されました。 手段的日常生活動作とは、掃除・料理といった家事や金銭管理、交通機関の利用などの生活を営むのに必要な複雑な動作をおこなう能力のこと。この能力が衰えてくると、自立した生活を続けるのが難しくなっていきます。 今回の研究は、医療経済研究機構(IHEP)が、愛知県豊明市やNTTデータ経営研究所と共同で実施したもの。その研究結果は「BMC Public Health」という学術誌に掲載されています。 高齢者の移動手段を「能動」と「受動」で分類 研究グループは、豊明市在住の要介護認定を受けていない高齢者を対象にした「住民健康実態調査」の2016年と2019年の調査結果を分析しました。 ちなみに、「住民健康実態調査」の対象者の詳細は以下のとおりです。 場所:愛知県豊明市在住 年齢:65歳以上の高齢者 人数:8145人 また、研究グループは対象者を移動手段ごとに分類。徒歩や乗用車(自分で運転)、電車・バス、自転車など自分で操作したり道を選択したりする「能動的移動手段」と、タクシーや乗用車(他者が運転)のような乗車だけで移動が完了する「受動的移動手段」に分けて、手段的日常生活動作の3年間の推移を調べました。 受動的な移動手段を使っている人は 研究グループが分析した結果、受動的移動手段を多く用いている高齢者は、能動的移動手段を多く用いている高齢者に比べて、家事や交通機関の利用など生活に欠かせない複雑な動作をおこなう能力「手段的日常生活動作」の低下リスクが1.93倍高まることが明らかになりました。 研究グループは「高齢者が受動的移動手段を選択することは、手段的日常生活動作の低下リスクと関連がある可能性が示された。自治体などの移動支援では、高齢者がバスや電車などの能動的な交通手段を利用できるような機会と環境を整えることが、高齢者の社会的自立を促すのに効果的なのではないか」と述べています。 能動的な移動手段には、もちろん徒歩も入ります。社会的に自立した生活を続けていくために、散歩する機会を定期的に設けてみても良いかもしれませんね。
2023/05/10
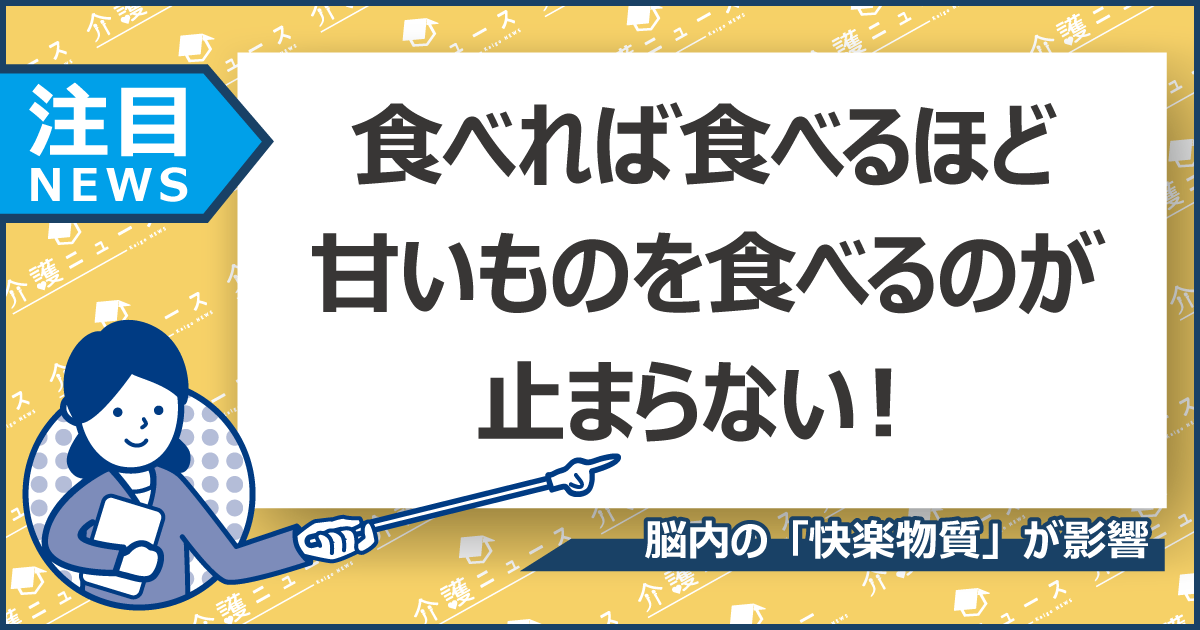
甘いものは食べるほどやめられない!?糖尿病予防に低カロリー甘味料を活用
新たな研究で、菓子パンやポテトチップス、ジュースなどの糖質の多い食品を日常的に摂取していると、脳が学習して甘いものを食べるのをやめられなくなることが示されました。 この研究は、ドイツのマックス・プランク代謝研究所とイェール大学が共同で実施したものです。 対象者の脳の変化を分析 研究グループは、50人の研究参加者を対象に、比較試験を実施。まず、参加者を2つのグループに分類しました。 1つのグループには通常の食事に加えて、糖質や脂肪を多く含むプリンを食べてもらいました。また、もう一方のグループには、糖質や脂肪の少ないプリンを食べてもらって、8週間後にそれぞれの対象者の脳にどのような変化が起きているかを分析しました。 甘い食品を食べ過ぎると脳内でドーパミンが増加 調査の結果、糖質や脂肪を多く含むプリンを食べてもらったグループでは、脳内のドーパミンの働きが活性化していたことが明らかになったのです。 ドーパミンとは、「快楽物質」とも呼ばれている神経伝達物質のこと。ドーパミンが分泌されると、多幸感や快楽を感じると言われています。糖質を多く含む食品を食べたときに脳内でこのドーパミンが分泌されることにより、脳は「糖質を多く含む食品を摂取すると幸福感を感じる」と学習し、甘いものを食べたり飲んだりするのをやめられなくなるのです。 今回の研究をリードしたマーク・ティットゲマイヤー氏は「糖質を多く含む食品を取り過ぎると、脳はそうした食品を食べると幸福感を感じることを学ぶ。そのため、過剰に糖質を多く含んだ食品を摂取していると、無意識のうちに高カロリーの食品を欲しがるようになる」と説明しました。 糖質の取り過ぎは体に良くないとはわかってはいるものの、どうしても甘いものを食べたいときもありますよね。最近では、糖類やカロリーを抑えた甘味料を使った食品や飲料もあるため、甘いものを食べたくなったら、甘味料を使った低カロリー食品を手に取ってみても良いかもしれませんね。 参考:「Sweets change our brain」
2023/05/02
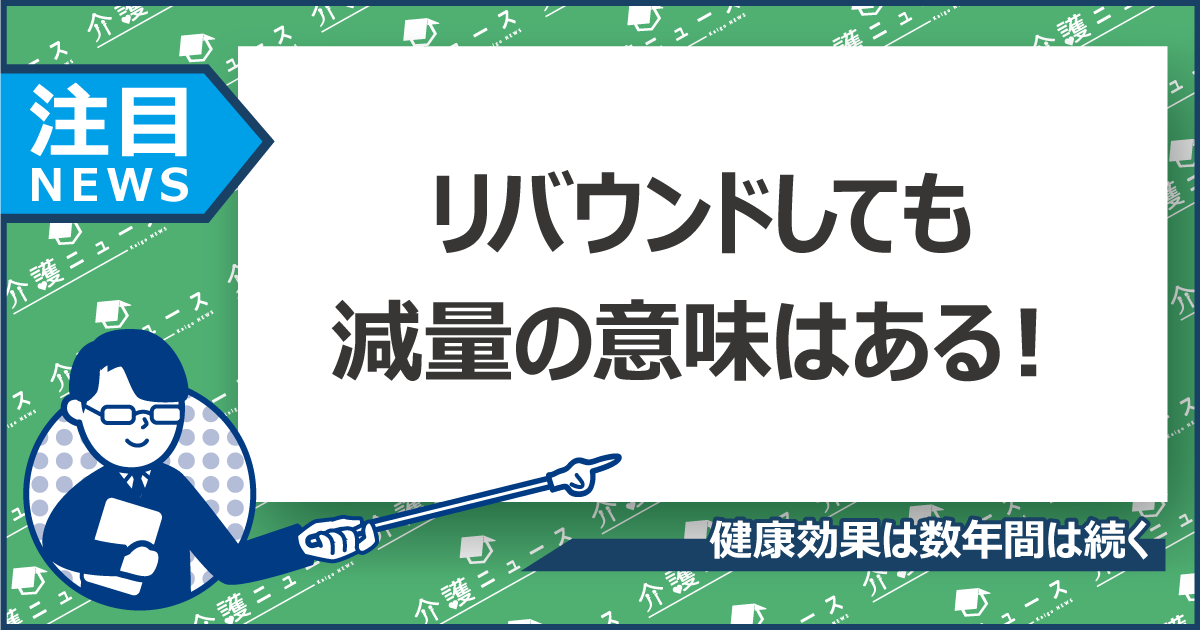
リバウンドしても糖尿病リスク低下効果は継続!?減量は無駄にならない
新たな研究で、減量後に体重が戻るリバウンドを経験しても、その過程で得られた健康効果は数年間持続することが明らかになりました。 この研究は、米国心臓学会が発表したものです。 集中的な減量プログラムの効果を測定 研究グループは、集中的におこなう減量プログラムの効果を測定するために、124件の国際的な研究を評価。集中的な減量プログラムに参加した人と参加しなかった人との、心血管疾患と糖尿病の危険因子を比較しました。 対象となった参加者の情報は以下のとおりです。 対象者数:5万人以上 平均年齢:51歳 肥満かどうかを測る体格指数(BMI)の平均33(肥満) また、対象者が取り組んだ活動は食事療法や運動療法で、その方法は対面による個別・グループ指導をはじめ、スマートフォンのアプリや電話によるオンライン指導、金銭的な動機付けを設定したものなどさまざまだったそうです。 プログラム終了後も健康効果が持続 研究グループが対象者のデータを解析した結果、減量プログラムに参加した人は参加しなかった人に比べてより減量し、心筋梗塞などの心血管疾患や糖尿病の発症リスクも減少したことが判明。また、プログラム終了後も、健康効果は数年にわたって続くことが明らかになりました。 具体的には、減量プログラムに参加した人は以下のような効果を得られることが示されたのです。 最高血圧の数値が、減量プログラムに参加してから1年後に平均して1.5mmHg低下。5年後にも平均0.4mmHg低下 1~2ヵ月の血糖値の平均が反映されるHbA1cは平均0.26%低下。1年後と5年後を比較してもその効果は変わらず 善玉コレステロールと総コレステロールの比率も1.5ポイント低下。1年後と5年後で効果は変わらず さらに研究グループが調査したところ、いくつかの先行研究では、減量プログラムに参加後に体重がリバウンドしてしまった人でも、心血管疾患や糖尿病の発症リスクは依然として低下したままであることがわかりました。 オックスフォード大学プライマリケア健康科学科に所属するスーザン・ジェブ氏は「減量プログラムに参加して体重を減らし人は、リバウンドをしたとしても数年にわたって心血管疾患のリスクを減らせることが明らかになった。減量に取り組んだことは無駄にならない」と述べています。 減量にはランニングや水泳などの有酸素運動が効果的だと言われています。長く健康に過ごすためにも、日々の生活に運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。
2023/05/01
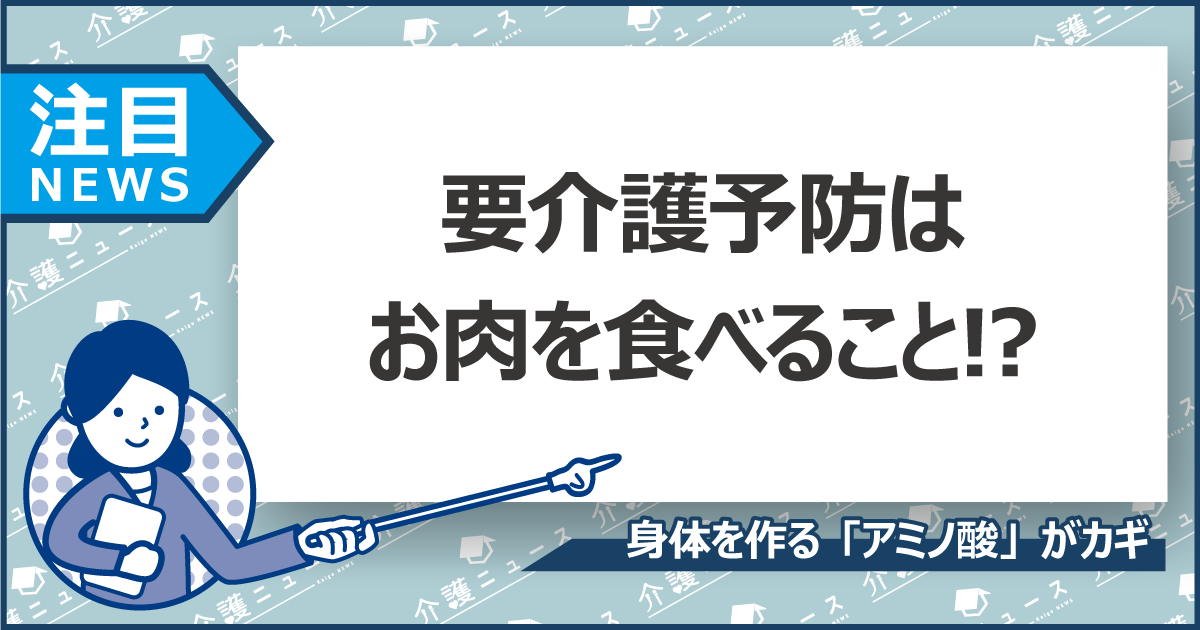
肉類を多く食べると要介護になりにくい!?歩行速度の速さと関連
新たな研究で、肉類を多く摂取している高齢者は、そうでない人に比べて歩行速度が速いことが明らかになりました。 歩行速度の速さは、身体機能を測る尺度のひとつとされています。 今回の研究は、東京都健康長寿医療センター研究所によっておこなわれ、その研究結果は「日本サルコペニア・フレイル学会誌」に掲載する予定だそうです。 アミノ酸が豊富な肉類に着目 今後さらに、高齢化の進展が見込まれています。厚生労働省の試算によると、2040年には全体の約35%が65歳以上の高齢者になると考えられているそうです。 そこで、課題となるのが要介護状態の前段階と呼ばれる「フレイル」対策です。フレイルとは、加齢によって心身の機能が衰えた状態のこと。フレイル状態を放置すると要介護へと進んでしまいます。 しかし、適切な介入があれば、フレイルから健康な状態に戻れるため、早い段階で対策を打っていくことが大切です。 今回、研究グループは健康な体をつくるアミノ酸が豊富に含まれている「肉類」に着目。肉類の摂取量とフレイルの関連性について調べました。 肉類をよく食べる高齢者は歩行速度が速い 研究グループは、同研究所が実施している健診に参加した高齢者512人を対象に調査を実施しました。 調査では対象者の食事内容、歩行速度、握力、血液の成分を測定・調査。対象者を肉類の摂取量で3グループに分け、フレイルに関連する指標である歩行速度との検討をおこないました。 その結果、肉類の摂取量が多い人は、そうでない人に比べて最大歩行速度が最も速い(フレイル状態になりにくい)ことが明らかになったのです。 研究グループはこの研究の意義について「今回の研究で、高齢期のフレイル予防の栄養ケアとして、肉類が有効である可能性を示せた」と述べています。 フレイル予防には、肉類を含めた栄養バランスの取れた食事が大切だと言われています。噛む力が衰えて肉類をうまく噛めなくなってきた人は、長時間煮込んで柔らかくするなど工夫してみると良いかもしれません。 参考:「平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容」(厚生労働省)
2023/04/27

特別養護老人ホームの約半数が赤字!?やはり人件費が経営を圧迫
2022年7~10月、全国老人福祉施設協議会は特別養護老人ホーム(特養)を対象にした、収支状況に関する調査を実施。今回、その調査結果が公開されました。 調査の結果、赤字で運営している特養が半数近くに上ることが明らかになったのです。 全国の特養に対して収支状況に関する調査を実施 今回の調査は、以下の要領で実施されました。 調査時期:2022年7~10月 対象:全国の特別養護老人ホーム 有効回答数:2246 この調査は、WEBシステムにある調査票をダウンロードして記入する形式でおこなわれたものです。 赤字で運営している特養が半数近くに 特養の収支状況を調査した結果、赤字で運営している施設が全体の43%と半数近くに上ることが明らかになりました。 また、赤字で運営している施設を種類別に見ると、小規模な居室空間でケアをおこなう「ユニット型特養」で約30%、多床室が中心の「従来型特養」で50%、ユニット型個室と多床室の両方がある「混合型特養」で45%という結果になりました。 以上のことから、施設の規模が大きくなるにつれて費用がかさみ、赤字で運営せざるを得ない状況に置かれている施設が多いと考えられます。 施設を運営する上で特に比率が高くなるのが人件費。その比率を調べたところ、66.2%でした。この数値は、調査を開始した2002年度以降、ほぼ毎年上昇傾向にあるそうです。 また、人件費比率を黒字施設・赤字施設別に見ると、黒字で運営できている施設では62.6%であるのに対し、赤字で運営している施設では70.9%とより人件費がかさんでいることが判明しました。 人件費は施設の財政を大きく圧迫しますが、これをカットすると余裕を持ったケアが難しくなり、介護サービスそのものの質の低下も懸念されます。介護サービスの質を維持していくためにも、政府には基本報酬の加算などの対応をしてほしいですね。
2023/04/25
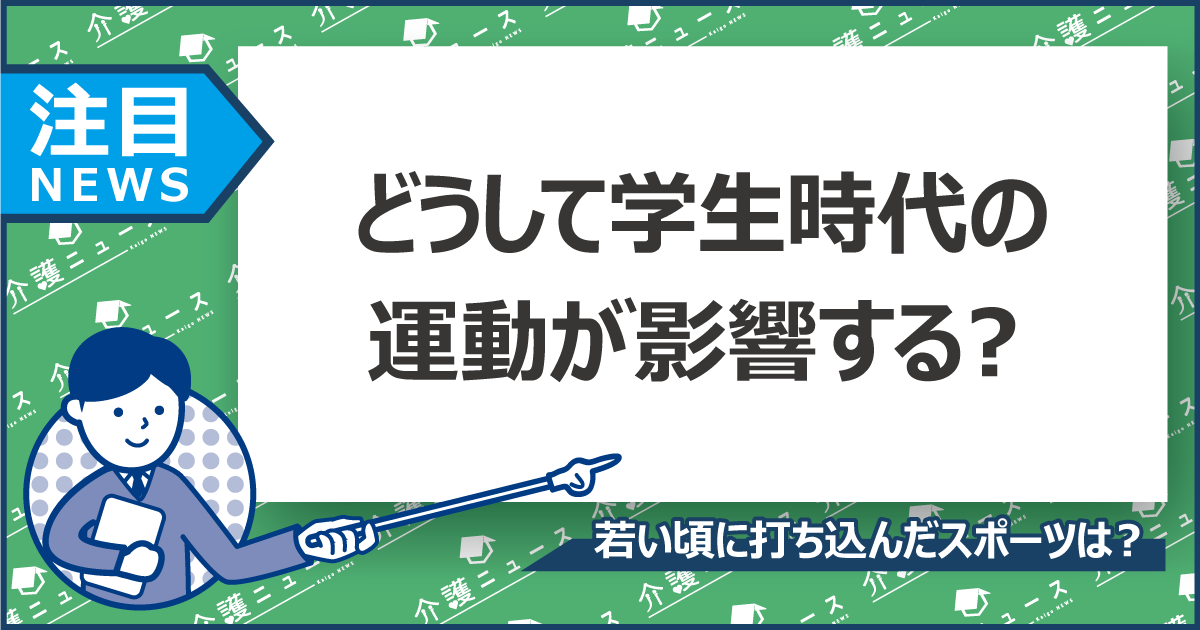
高齢期の筋肉量に中学・高校時代の運動習慣が関係!?若い頃の運動が大切
新たな研究で、中学・高校生期と高齢期の両方に運動習慣がある人は、そうでない人に比べて加齢や疾患で筋肉量が減少する「サルコペニア」になるリスクが低下することが示されました。 この研究は、順天堂大学の研究グループによっておこなわれ、その研究結果は「Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle」という医学誌に掲載されています。 サルコペニアとは そもそも、サルコペニアとはどのような状態なのでしょうか? サルコペニアとは、加齢や疾患により骨格筋の筋肉量が著しく減少した状態のこと。この状態になると、日常生活の動作に欠かせない筋力も衰えるため、転倒や骨折などで要介護状態になるリスクが高まります。 そのため、高齢になっても健康で長く過ごしていくには、サルコペニアの予防が大切です。 中学・高校期の運動習慣がサルコペニアを予防する 研究グループは、20~25歳でピークを示し、50歳前後から徐々に低下していくという骨格筋機能の推移に着目。ピークを高める中学・高校生期と低下を抑える高齢期で運動をおこなえばサルコペニアを防止できるのではないかと推測しました。 そこで、研究グループは順天堂大学がおこなっている、東京都文京区在住の高齢者を対象にした観察型研究「文京ヘルススタディー」の参加者1607人を対象に調査を実施。中学・高校生期および高齢期の運動習慣と、サルコペニアの発症リスクとの関連性について解析しました。 解析の結果、男性では中学・高校生期と高齢期の両方で運動習慣がある人は、両時期に運動習慣がない人に比べて、サルコペニアを有する人の割合が0.29倍低いことが明らかになったのです。また、筋力や身体機能が低下した人の割合も0.52倍低いことがわかりました。 さらに女性でも、中学・高校生期と高齢期の両方で運動習慣がある人は、どちらの時期にも運動習慣がない人に比べて、筋力や身体機能が低下した人の割合が0.53%低いことが判明。一方、女性ではサルコペニアを有する人の割合には差が見られませんでした。 以上の結果を受けて、研究グループは「若い頃の運動の長期的な意義がこの研究で示された。若い頃に参加しやすい運動やスポーツの機会を増やしていくことが大切だ」と述べました。 今回の研究で、若い頃の運動の大切さが示されました。ただ、中学生や高校生の頃は文化部だったという人もいるでしょう。そんな人は、今からウォーキングなどの軽い運動をすることから始めてみてはいかがでしょうか。 今回の研究以外にも、運動の効果を示す研究はたくさん世に出ています。今からでも運動習慣をつけることは、決して無駄にはなりませんよ。
2023/04/21
よく読まれている記事
よく読まれている記事
特集
介護の基礎知識


介護の悩みを
トータルサポート

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。

















