
特集
ブックレビュー

『ポテトチップスと日本人』─「ポテチから見た日本社会の変容史」に効く1冊
今回取りあげるのは、稲田豊史氏の最新刊。『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)で新書大賞2023第2位を獲得した著者である。 「日本においてポテトチップスは、スナック菓子売り場でもっとも良い場所に陳列されていて、その種類は目移りするほど豊富だ」と語るポテチが、いかにして「日本人の国民食」となっていったかを丁寧に追った労作だ。 『ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生』 著者:稲田豊史 発行:朝日新書 定価:950円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ じゃがいもは、人々に好まれる食べ物ではなかった 本書の冒頭で明かされるのは、ポテチの原料であるじゃがいもが、世界において蔑視される食材だったという意外な事実である。 16世紀頃、原産地の南米アンデス山脈からヨーロッパに渡ったジャガイモは、生産効率が高く、栽培もしやすいことからまたたく間に各地へ広がったが、その地位は低かったという。その理由は、次のように説明される。 なぜなら当時のヨーロッパでは、人間が食すことのできる植物はすべて種から育てるものであり、「雌雄が受精によって結ばれ実を結ぶのではなく、種芋が自己増殖する」という“異常な性質”がキリスト教的に“不潔” である、とする考え方があったからだ。(中略)英語圏においてはジャガイモ (potato) はネガティブな言い回しとして使用されている。 「hot potato」 は「誰も責任を取ろうとしない企画」、「meat-and-potatoes man」 は 「単純な味覚の持ち主の男性」、「potato head」 は ...
2023/05/19

『おやじはニーチェ』─「“哲学”をツールにした認知症理解」に効く1冊
今回紹介するのは、第10回小林秀雄賞を受賞した『ご先祖様はどちら様』をはじめ、ドラマ化もされた『「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー』(いずれも新潮社)などの傑作ルポで知られる髙橋秀実氏の最新刊である。 ヒデミネ氏の作品リストのなかには、自らの日常を題材にしたものも多い。カナヅチを克服すべく水泳教室に通う日々を綴った『はい、泳げません』、妻とともにダイエットに奮闘努力する『やせれば美人』(いずれも新潮社)など、自らの体験をユーモラスに語った抱腹絶倒の「自分ルポ」は、どれも傑作だ。 『おやじはニーチェ』も、認知症になった父と過ごした436日の日々を題材にしているという点でその系譜に入る作品だが、他の作品と比べてちょっと重苦しい雰囲気があるように感じた。認知症介護には、ユーモアだけで語れない、シリアスな面があるからなのかもしれない。 とはいえ、この作品がおもしろくないのかというと、そうではない。それどころか、認知症に新たな視点を得られる有意義な書だとも言える。ところどころで発揮されるヒデミネ節をたどりながら、本の内容をレビューしていこう。 『おやじはニーチェ 認知症の父と過ごした436日』 著者:髙橋秀実 発行:新潮社 定価:1650円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ ある日突然始まった、認知症の父との同居生活 ヒデミネ氏が父の認知症を意識したのは、母が急逝したことがきっかけだった。引用しよう。 以前から父は同じ話を何度も繰り返していた。最近の出来事も丸ごと忘れており、忘れたことも忘れているようで私は「大丈夫なのか?」と心配していたのだが、母は「大丈夫よ」の一点張りだった。つまり不都合のないように都合をつけて生活していた。私たち息子夫婦の生活を阻害せず、不都合をかけまいと頑張っていたのだ。ところが母は急性大動脈解離で突然この世を去った。87歳だった父は取り残され、すべてが不都合になった。母の不在で露わになった認知症というべきか。 介護は、ある日突然、必要が生じて、それがゆえに家族は何ひとつ準備をしていない状況から介護を実行しなければならない。 ただ、ヒデミネ氏の場合、父親は身体的には健康なので、食事や排泄、衣類の着脱といった「生活介助」の必要性は薄い。実際に彼は地域のケアマネジャーの小暮さん(仮名)から、「受けられる介護サービスって、あんまりないんですよね」と告げられる。 ケアマネジャーの小暮さんも残念そうにそう言った。父はすでに区役所から「要介護3」の認定を受けており、私は小暮さんと「居宅介護支援」の契約を済ませていた。彼を通じて様々な介護サービスを受ける予定だったのだが、「お父さんの場合はちょっと……」とのことなのである。例えば、認知症の介護でよく利用される「デイサービス」。車で迎えに来てくれて父をしばらく預かってくれるというサービスなのだが、おそらく父はひとりでは車に乗らないだろう。無理やり乗せようとすれば「なんでだ!」と怒号をあげるので私が同行しなければならず、途中で「帰る!」と言い出さないようにデイサービスの施設でも付き添うことになる。ずっと付き添うのではデイサービスの意味がないのだ。 同じような困難は「特別養護老人ホーム」への入居にも言えて、満杯で数百人が待機しているという施設において、要介護の緊急性が高いヒデミネ氏の父の入居はすぐに認められるというが、入所すれば「なんでだ!」「帰る!」などと言い出して勝手に施設から出ていってしまう人は再入所がむずかしくなるというのだ。 そこでケアマネジャーから提案されたのは、月に2万円ほどの自己負担で、家に緊急通報用の電話が設置され、ヘルパーが1日に何度も家に来てくれる「定期巡回・臨時対応型訪問介護看護」だった。 とはいえ、身のまわりの世話の一切を引き受けていた母の家で父ひとりを置いていくわけにはいかない。ヒデミネ氏は妻とともに、実家で父との同居生活を始めることになる。 「哲学」をツールにして認知症を理解するということ ヒデミネ氏は、認知症の父がどのような世界に生きているのかを知ろうとして、さまざまな会話を試みる。 例えば、自分はなぜいまここにいるのか、ここはいったいどこで、いまはいったいいつなのか?という、医療介護用語で見当識と呼ばれる能力をテストするつもりで「ところでさ、俺たちが今いるところはどこ?」と質問する。そこで以下のような会話が交わされる。棒線以下のセリフがヒデミネ氏の発言で、カッコ内が父のセリフである。 「どこが?」父はそう問い返した。――どこがって、ここが。私は床を指差した。「ここがどこかって?」そう、ここはどこ?「どこが?」――ここが。「どこ?」――いや、だからここ。「だからここってどこだ?」――だからここじゃなくて、ここ。「どこ?」――ここ。「ここってどこだ?」 このように会話は堂々めぐりをしてヒデミネ氏を混乱させる。 記憶力をテストしようとして、「今日は何をしてたの?」と質問したり、自分が認知症であるという病識があるかどうかを知ろうとして、「認知症って知ってる?」と聞いても同じような結果になる。 頭を抱えたヒデミネ氏が助けを求めたのが、古今東西の哲学思想である。 例えば、「万物は永久に回帰し、われわれ自身もそれとともに回帰する」というフリードリッヒ・ニーチェの「永遠回帰」の考えと照らし合わせて、記憶力を失うということをこう解釈する。 私たちは忘れるから幸福になれる。失敗を忘れるから夢や希望も抱けるし、忘れるから現在を感じられるという。すべてのことをそのまますべて記憶していたら、それこそ自縄自縛の境遇に陥って前に進めない。経験が記憶によって生まれるのであれば、記憶を消去することで初めて新しい現実と出会えるのだ。ありがたき忘却力ということか。 このように、哲学思想が認知症理解に新たな視点を当てるのである。ヒデミネ氏は学生時代から「哲学」というものに馴染めず、嫌悪感すら抱いていたそうだが、認知症理解のツールと考えた途端、すらすらと理解できるようになったという。 そこで介護のかたわら、プラトンやアリストテレス、デカルト、ニーチェ、サルトル、ベルクソン、西田幾多郎、九鬼周造などの哲学書を読みふけったというが、それが認知症理解の助けになったにせよ、介護の大変さ、つらさから逃れられるわけではなかった。 ある日、「『存在』とか言ってる場合じゃないでしょ」と妻に指摘され、うろたえるヒデミネ氏。父と24時間休みなく向き合うなか、仕事もできずに経済的にも追いつめられた彼は、父との別居を決意せざるを得なくなるのである。 認知症介護はある日突然始まって、ある日突然終わる 別居したとはいえ、介護から完全に解放されるわけではない。クルマで40分の場所にある実家と自宅を往復しながらの介護は続いていく。 自分のことを「息子」として認識せず、「社長」とか「お兄ちゃん」とか、「旦那」などと呼ぶ父との対話を続けていく。そして、哲学の視点からの認知症理解に取り組む。「あとがき」で自身が告白しているように、それが「日常生活の逃避行」であると自覚しながらも。 こうした終わりの見えない介護生活は、父が「末期の胃がん」におかされていたことが発覚して急展開を見せる。 病院は介護施設ではないので、治療が終了すれば退院を迫られるが、医療ソーシャルワーカーと相談しながら父の処遇を決めなければならない。終末期医療専門のホスピス病院や有料老人ホームもあるが、どこも待機人数が多く、いつ入所できるかわからない。 幸いなことに「認知症があると転院はむずかしい」と言われていた緩和ケア病棟に移ることができたのだが、それ以前に入所を打診した小規模介護施設からは「早く決めないとすぐに埋まっちゃうわよ。行くとこなくて困ってるんでしょ」と姥捨山のような対応をされて閉口したという。 それでもヒデミネ氏は、最後まで父との対話を繰り返し、それをメモして記録していく。 そして、自分のことを28歳だと思っていて、緩和ケア病棟の部屋に同室している自分を女性だと勘違いして口説いてくる父と、ビデミネ氏は実に感動的な会話をするのである。 この場面は、是非とも本書を手にとって読んで欲しい。ことさら感動を演出するかのようにして書かれてはいないが、私は大いに心を動かされた。 本書は「認知症とは何か?」ということについて、ヒデミネ氏が真摯に向き合った記録として読めるが、そこに明確な解答があるわけではない。というか、明確な解答などないというのが、ある意味での結論なのかもしれない。 少なくとも、認知症を知る上で、本書は新たな視点を与えてくれる書であることに間違いはないだろう。
2023/05/12

『私の親鸞』─五木寛之の語りに潜む「親鸞ワールドの不思議」に効く1冊
五木寛之という名は私にとって、「ベストセラー作家」「流行作家」の代名詞だった。 直木賞受賞作の『蒼ざめた馬を見よ』(文春文庫)や大河小説『青春の門』(講談社文庫)といった代表作はもちろんだが、昭和41年生まれの私には翻訳を手掛けたリチャード・バックの『かもめのジョナサン』(新潮文庫)や烏丸せつ子主演で映画化された『四季・奈津子』(集英社文庫)のイメージが強い。 どの作品も、出版と同時に話題となり、風にたなびく長髪、サングラス、タートルネックのセーターにジャケット姿の「著者近影」の写真パネルが書店の平積みされた新刊の棚に飾られていたものだった。 その、あまりのハマりっぷりに、まだ七三分けで『笑っていいとも!』に出ていたタモリが、名古屋弁をしゃべる人や週末ゴルフに興じる俗物たちと同列に「深刻がって気取っている」とやり玉に挙げて腐していた記憶がある。 その五木寛之氏が2010年代に入って、親鸞の生涯を綴る大河小説『親鸞』(講談社文庫)という大著を手掛けたことを知ったときは、「どうして?」という、ちょっとした違和感があった。 浄土真宗の宗祖であり、「他力本願」、「悪人正機」などの思想を後世にもたらした親鸞聖人と、カッコいい「流行作家」としての五木寛之氏のイメージが結びつかなかったのである。 なぜ、五木寛之は親鸞に関心を持ったのか? 実は本書は、89歳になった五木氏が、その質問に全力で答えた書のような気がする。その秘密について考えながらレビューしていこう。 『私の親鸞孤独に寄りそうひと』 著者:五木寛之 発行:新潮選書 定価:1350円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ なぜ五木寛之は「親鸞」に魅せられたのか? まずは冒頭の文章を引用する。 「そもそも、どうして五木さんは浄土真宗に関心を?」以前、上智大学で宗教学者の島薗進さんと対談させていただいた際、鳥さんにそう聞かれましたが、べつに理由というほどのものはないのです。ただ、物心ついたときには家に仏壇があり、その前で両親が時々お勤めをしていた。そのとき両親が唱えていたのが「正信偈(しょうしんげ)」で、はやく亡くなった母親にこう言われたこともありました。「ヒロちゃんがね、まだ三つか四つぐらいの頃、私たちが正信偈をリズムをつけて唱えると、後ろでそれに合わせてタコ踊りみたいな踊りを踊ってたのよ」 「正信偈」とは、親鸞の主著『教行信証』のなかの一節で、浄土真宗の門徒が朝晩の勤行でよく読む偈(詩)文のこと。 つまり、島薗氏の質問に「生まれた家が浄土真宗の檀家だったから」と答えたのだが、どうもそれだけではないような気がする。 というのも、私は幸運なことに昨年の3月、89歳の五木氏にインタビューする機会をいただき、島薗氏と同じ質問をしてみたところ、上記とは別の答えが返ってきたからだ。 そのときの答えは、この本でも触れられている。 私が金沢に住んでいた三~四十年ぐらい前は、金沢の至るところに「一向一揆の跡」という札が立てられていたものです。たとえば、枯木橋という橋のたもとには、「一向一揆のとき、この辺りは戦火に巻かれて全ての家が焼失した。その家々の柱が枯れ木のように残っていたので、枯木橋と呼ぶようになった」などという説明が立て札に出ていたものです。 金沢は妻・玲子さんの郷里で、金沢を舞台にした小説もたくさん書いている五木氏だが、そこに住んでいる間に史跡を見つけて興味を持ったというのがその答えだった。 五木氏は「なぜ親鸞に興味を?」という質問に答えるのが嫌で、わざとバラバラの返答をして質問者を煙に巻いているのか? いや、そういう感じではなかった。少なくとも私はそう感じた。要するにこの質問は五木氏にとって、簡単に答えられる種類の質問ではないようなのだ。 学べば学ぶほど遠ざかっていく「まぼろしの親鸞」 代わりに五木氏が語るのは、12歳のときの朝鮮半島からの引き揚げ体験だ。 政府からの援助はなく、戦争が終わっても北朝鮮の平壌(ピョンヤン)に抑留されるような形で暮らしていた五木氏の一家は、結局、徒歩で三十八度線を越えて開城(ケソン)付近にあった米軍の難民キャンプに逃げのびたのだが、「その過程を通じた一年から二年間のうちに体験したことは、できることなら思い出したくないことばかり」だと語る。 たとえば、国境線を越えるトラックに、「あと二人乗れるよ」と言われて、何人かが先を争って荷台によじ登ろうとします。すると先に上った二人は、後から乗ろうとする仲間を足で落とし、あるいは突き落として車を出してしまうしかない。 つまり、他人の命を犠牲にして生き残った自分は、悪人である。許されざる者である。つねにそういう意識があったと五木氏は告白する。 そして、30歳を過ぎた頃、親鸞の考え方や教えに触れて「ああ、ひょっとすると、この人の考え方によって自分は救われるかも」という感覚を得たという。 おそらくこれが、「なぜ親鸞に関心を持ったのか?」という質問に対する、五木氏の心の芯に近い部分から出た答えなのではないか。 だが、この告白には続きがある。 親鸞についての多くの本を読み、寺にも通い、一時は休筆して龍谷大学の聴講生にもなったりもして、大河小説『親鸞』(講談社文庫)をものにしても、30代のときに感動した親鸞の像がどんどん向こうへ遠ざかっていって、まぼろしのようにしか見えなくなってしまったのだという。 「生身の親鸞を知りたい」という心の叫び なぜ親鸞は、学ぼうとすればするほど遠ざかってしまうのか? 五木氏は自問する。そして、次のような結論を得るのである。 吉本隆明さんや梅原猛さんをはじめ、これまで親鸞に関しては多くの知識人による高度な思索が繰り返されてきました。それらの本は気軽に書店で買うこともできます。しかし、「二人いて喜ぶ時は、その一人は親鸞だと思え。三人いて喜べば、その中の一人は親鸞だと思え」という親鸞の言葉、お遍路さんの「同行二人」のように、自分のそばで支えてくれて、後ろから肩を抱いてくれるような存在。そんな親鸞像がにわかに雲の上の高みに持ち上げられて、人々はそれをふりあおがなければならない、そんな存在に変わった感じがします。 別のところでは、こんな風にも説明している。 おかしな言い方ですが、「まぼろしの親鸞」というのは、抽象化された親鸞、ということですね。親鸞が生きた人の姿で、こちらの肩に手を置いて語りかけてくるような存在として 考えられるのではなくて、観念として、あるいは一つの思想としてのシンボルのように感じられてしまう。それが今の親鸞学の問題点だろうと私は思うのです。私たちは、親鸞の生の声を聞きたい。生の表情を想像したい。そういうものが伝わってく るようなものを知りたい。けれども現実には研究すればするほど、分析すればするほど、人 間の実体から遠ざかっていくような傾向があるのではないでしょうか。 本書では、五木氏が「生身の親鸞を知りたい」という欲求に従って、隠れ念仏の里を訪ねたり、弟子の唯円が晩年の親鸞の言葉をまとめたと言われる『歎異抄』を読み解いたりした、さまざまな経験が語られるのである。 「粗雑」で「乱暴」な語りに見える「真実」 最初に断っておくべきだったかもしれないが、本書は少人数の聴衆のために語りおろした話を文章にしたものに、その他の場所で書いたものを加えてまとめたものだという。 そのため、五木氏自身、「読み返してみると、まことに粗雑な感じがします」とか、「乱暴で非常識な発言も少なくありません」などと批評している。 いや、語りおろしなんだから、謙遜したんじゃないかと思う人もいるかもしれないが、確かに読んでみると、「粗雑」「乱暴」という言葉を否定できないレベルで全体的に散漫な印象を受けるのだ。 決して読みにくいわけではないが、話がとりとめもなく別の話に飛んだかと思うと、同じ話が2度出てきたりして、どうにも落ち着かない。 例えば、『歎異抄』のなかの「親鸞は弟子一人も持たず候」という言葉の引用は、私が数えた限りで本書に3回も出てくる。 実際には親鸞には多くの弟子がいて、京都での晩年の親鸞の生活を支えていた。最初の引用では、そのことについて、次のような説明がつく。 ですから、弟子一人も持たず、とは弟子は現実にはいるかもしれないが、自分は弟子だとは思っていない。つまり御同朋(ごどうぼう)、同じ仏の道を極めていく対等な仲間であるのだと言っているわけです。これは心がけ、心もちであって、現実との落差をどう埋めていくのかという、大きな問題だと思います。 3回目の引用では1回目の趣旨と違って、次のように語っている。 私はこの「弟子一人も持たず候」という言葉を読んだとき、そこに親鸞の深い孤独感、寂寥感のようなものを感じて、ため息をつきました。親鸞を師とあおぎ、遠方から難路をこえてその教えを乞うためにやってくる念仏者も少なくない。しかし、どれほど親鸞が言葉をつくしても、その真意を底まで理解する弟子は少ない。いや、いないのではないか。それは当然です。親鸞は信仰において、学識において、その思索の深さにおいて、屹立した存在でした。 このふたつの引用を比較してみると、それは単なる繰り返しなのではなく、ひとつの言葉を角度を変えて何度も見つめ直しているのだということがわかる。 そう考えてみると、本書の「粗雑」で「乱暴」な文体は、五木氏が「できることなら思い出したくない」と語る「引き揚げ体験」にも関係しているようにも思う。 第一章で語られた引き揚げの話は、最終章の最後の最後で再び語られ、オチにつながるわけでもなく、ふと終わる。この不格好な形が、五木氏が語ったことの真実性を物語っているのではないか。とにかく私は、ズシンとした読後感を味わった。
2023/04/28

『源氏物語 解剖図鑑』─「現代語訳を読んで大河ドラマ『光る君へ』に備える」に効く1冊
2024年のNHK大河ドラマが紫式部を主人公にした『光る君へ』になると聞いたときはブッ飛んだ。なぜ令和の今に平安時代? 源氏物語は2008年の平成時代に成立1000年を記念した「千年紀プロジェクト」をやっていたから、そのときのほうがタイムリーだったんじゃないの? などと、しきりに首をかしげたのだが、大河ドラマというのは時代の流れに迎合するのではなくて、自ら流れをつくるという気概に満ちた国民的ドラマなのだから、まぁそういうものかとも思う。 現在放送中の『どうする家康』が終盤に近づく年末あたりになると、大河マニア、ならびに源氏ファンがそわそわしだして「どんな大河になるんだろうね」などと噂話が始まるのが目に見えている。 で、そんなとき、「ああ、『源氏物語』ね。まぁ、いちおう僕も読んでみたけど、おもしろいと思うよ。現代語訳だけどね」くらいのセリフは言ってみたい。そう思っている人は多いと思う。 『源氏物語』は世界最古の長編小説と言われるが、ただ古いだけでなくて、小説として読んでも本当におもしろい。ただネックなのが「長い」ということだ。意気込んで読みはじめて、平安貴族の風俗とか雰囲気に馴染めずに挫折してしまう人も多いだろう。だが、作品中の世界観が理解できるようになると俄然、読むのが楽しくなるのだ。 というわけで今回は、「『源氏物語』を最後まで読む」という目標にゴールするためのアプローチ法を提案したいと思う。 『源氏物語 解剖図鑑 』 著者:佐藤晃子/文、伊藤ハムスター/イラスト 発行:エクスナレッジ 定価:1600円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ 挫折して途中から再読しても、ガイドブックがあれば大丈夫 現代語訳にこだわらないのならば、「最後まで読む」にたどりつく最も手っとり早い手段が大和和紀による漫画『あさきゆめみし』を読むことだ。ストーリーはほぼ忠実に描かれていて、古文の受験対策として予備校も推奨しているらしいし、平安時代の衣服や建築なども膨大な資料をもとに考証されて描かれている。 同時期に現代語訳を手掛けた瀬戸内寂聴も、この漫画の完成度には高い評価をしている(ちなみに同じ漫画版では江川達也によるものがあって、こちらも評判が高い)。 でも、やっぱり漫画じゃなくて現代語訳で読みたい、という人もいるだろう。私もそうだった。 だが、その道を選んだ結果として、54帖にも及ぶ長大な物語に出てくる、430人もの登場人物を把握するという難題に直面することになる。ちょっと気を抜くと、「あれっ? このキャラクターって前にも出てきたけど、どんな人だったっけ?」と、すでに読んだところに戻ったりしているうちに、筋がわからなくなるのである。 そこでお薦めしたいのが、『源氏物語 解剖図鑑』(エクスナレッジ)のようなガイドブックを座右に置きながら読むことである。 さすがのエクスナレッジ「解剖図鑑」シリーズ この本の優れているところは、巻ごとのストーリーと、そこに登場する人物の関係性がコンパクトにまとめられているところ。「この人誰だっけ?」という疑問に即座に応えてくれるのである。さらに親切なことに、複雑にからみあった人間関係が図で説明されていたりもする。 要するに「この巻では、これだけの知識があればいいですよ」と必要な部分を強調してくれるので、読むガイド役として非常に優秀な仕事をしてくれるのだ。 途中で挫折してしまった場合、再チャレンジまでの時間が長くなるにつれ、記憶は定かでなくなり、結局「また最初から読み直さねばならなくなる→再度の挫折をうながす」という悪循環につながるが、このガイドブックがあれば途中からでも再チャレンジできる。これは大きい(巻末に索引があって、知りたいことにすぐにアクセスできる親切設計)。 また、平安貴族の風習や信仰など、必要な基礎知識をコンパクトに説明してくれているのも、物語の理解を助けてくれる。 こうしたガイドブックは、これまでにたくさん出版されてきたが、エクスナレッジの『解剖図鑑』シリーズの一冊である本書は、過去50冊以上作られたきたシリーズのノウハウが生かされていて、よくできていると思う。 与謝野訳、谷崎訳はなぜ読みにくいのか? ガイドブックの次に選ぶべきは、「誰の現代語訳で読むか?」ということ。実はこの選択こそ、ガイドブック選び以上に重要なのだ。 「いちおう読んでみたけどね」などと偉そうに語った私だが、実は過去には与謝野晶子訳、谷崎潤一郎訳という2つの現代語訳に挑んでいずれも挫折し、2013年に出版された林望訳『謹訳 源氏物語』の最終巻でようやく全巻を読破したヘタレ源氏読みである。 与謝野訳、谷崎訳は、自身も現代語訳を手掛けた橋本治が「2大クラシック現代語訳」と評する名作だが、すでに訳業から70年以上も経っているので、それぞれに読みにくさがあるのだ。 強いてどちらがとっつきやすいかと言えば、与謝野訳だ。 与謝野晶子訳の「源氏物語」は和歌が訳されていない!? それには2種類があって、ひとつは1913(大正2)年に完成したダイジェスト版で、角川文庫ソフィアから『与謝野晶子の源氏物語』として全3冊で出ている。 もうひとつは1939年(昭和14年)に完成させた「新訳」で、そのあとがきに与謝野は前作の「略述」が「粗雑な解と訳文」だったので、より原文に近い形で書き直したと書いている。 とはいえ、ダイジェスト版が現在も出版されているということは、読みやすいからで、いずれも著作権フリーになっているので青空文庫などで無料で読めるという手軽さもある。 与謝野訳の唯一の欠点は、和歌が訳されていないということ。 実は『源氏物語』には795もの和歌が収録されていて、なかには登場人物が自分の心情を歌に託すシーンも多い。従って、和歌の意味がわからないとストーリーの理解があいまいになってしまうところがあるのである。 与謝野は自身も歌人だったから、当時の読者の和歌リテラシーを信用していたのかもしれないが、令和を生きる人にその能力を求めるのはむずかしいだろう。 谷崎潤一郎訳の「源氏物語」は文章自体が難解という致命的弱点が 谷崎訳について言えば、和歌がどうとかいう問題だけでなく、原文に近い形で訳されているので文章全体が難解そのものなのだ。 谷崎は序文で「あまり学究的にならずに、普通の人が普通の現代小説を読むやうな風に読んで頂きたい」とか、「原文と対照して読むためのものではない」と書いているが、「原文と対照して読むのにも役立たなくはない筈であり」などとも書いていて、結果的にその文章を読みにくくしているようだ。 円地訳、田辺訳、瀬戸内訳。女流作家3人による絢爛豪華な世界 昭和の時代に出版された現代語訳されたものには、円地文子、田辺聖子、瀬戸内寂聴の3作がある。 もちろん、私はこれら全文を読んだわけではないので、『痛快!寂聴源氏塾』(集英社文庫)のなかの寂聴の解説をここに紹介しよう。 「円地源氏」は、与謝野源氏とも、また谷崎の源氏とも違ったスタンスで書かれています。そのことについて、円地さんは、「人の愛し方には、相手をそっと床の間に置くように大切にする愛し方と、一方的な略奪結婚があるけれども、私の訳はその略奪結婚のほうね」とおっしゃっていました。「あくまでも原文に忠実に」をモットーにした谷崎源氏とは対極的に、円地さんはたとえ紫式部の原文には書かれていなくても、「私ならば、こう書く」と思ったところは自由に加筆されています。光源氏と女たちのベッドシーンなどがその例です。 ようするに谷崎のコンセプト、「普通の人が普通の現代小説を読むやうな風に」読めるものを円地流に実現したものだということがわかる。 次に、田辺聖子訳の寂聴評はどうだろう。こちらは『わたしの源氏物語』(小学館)からの引用だ。 古典を愛し、古典にいれあげて、広く深く読みこなし、しっかりと噛みくだき食べてしまって、自分の血や肉にしてしまった女流作家に田辺聖子さんがいる。おそらく当代女流の中では 田辺さんほど古典を読みこんでいる人はいないだろう。その田辺さんにも源氏物語を現代語訳ではなく、すっかり自分のものとして食べてしまった後で、改めて、繭糸を吐き出すようにして織りあげた『新源氏物語』という大作がある。これは源氏を下じきにした田辺さんの全く新しい小説といっていいだろう。面白さでは円地源氏よりずっと這入(はい)りやすい。 この田辺訳は、エピソードをばっさり切って、読みやすく、ドラマチックに並べ替えたりしてもいるので、現代語訳というよりは、翻案小説とも言えるだろう。 では、自身の現代語訳について、寂聴はどのように発言しているのか? そこで訳にあたっては、毛糸のようにもつれている源氏物語の長い文章のところどころにハサミを入れ、また主語もくどいほどに追加しました。また、源氏物語にかぎらず、古典の文章には敬語が多用されているのですが、これは読みやすく省略することにしました。しかし、それ以外は、原文にできるかぎり忠実に訳しています。(『痛快!寂聴源氏塾』) なかでも寂聴訳の特徴は、和歌を五行詩で訳しているところ。学校で古文を習ったことのある人なら、和歌の現代語訳が説明的で味気ないものだと知っていると思うが、これが興趣ある現代風の詩で味わえるのはありがたいかもしれない。 橋本訳、林望訳の男目線の魅力 続いては、男性作家による現代語訳を見ていこう。橋本治訳、林望訳の2つである。 橋本治訳『窯変 源氏物語』(中公文庫)の最大の特徴は、物語全体が主人公である光源氏、および薫の一人称で語られているという点である。これについて橋本はエッセイ集『源氏供養』(中公文庫)で次のように説明している。 私が源氏物語を「光源氏の一人称で語り直してしまえ」と思った最大の理由は、「自分がどこまで魅力的な“悪い男”になれるか試してみたい」ということです。こういうことが物語作者の特権です。「女流作家の完成させた女の世界を、“男の世界” として取り戻してやる」という、『ぼんち』の主人公のような気持が私の“悪”の正体なのですが、ということになると、文体というものを考えなければなりません。 私がリンボウ先生こと、林望訳『謹訳 源氏物語』(祥伝社)で初めて全巻読破を達成したことは前述したが、そのウラには、訳業が完成する前後に私が先生にインタビューしたことがある。現在、その記事はサイト閉鎖によって閲覧できないが、その一部をここに再現することにしよう。 作家が書いたもの、学者が書いたもの、そのふたつの現代語訳には特徴があって、簡単に言ってしまうと、前者が作家らしい大胆さで自由に訳したものだとすると、後者は学術的な解釈で厳密に訳されたものです。どちらにも長所と短所があって、一概に「これがいい」とは決めかねます。そこで私はそのふたつの特徴を統合してみようと思いました。つまり、作家の書き方で面白く、学者の分析力で正確に訳してみようというわけです。説明が必要な部分は書き足し、敬語など古文特有のまわりくどい言い回しなどは省略し、現代人が面白く読むことができて、なおかつ源氏物語の格調高い文学のエッセンスをわかりやすく伝えられるようなものにしたいと考えました。 リンボウ先生と言えば、デビュー作でありベストセラーにもなったエッセイ『イギリスはおいしい』(文春文庫)のイメージが強いからか、しばしば英米文学者だと誤解されることがあったそうだが、実は先生の専門は国文学、書誌学であり、「『源氏物語』の現代語訳に取り組みたい」という願望は作家デビューしたばかりのころから持っていたそうだ。 とにかく、その先生の労作のおかげで私は「源氏の現代語訳読破」を何とか達成できたわけである。感謝しかない。 まだまだあるぞ現代語訳。できれば2周目、3周目に挑戦したい さて、最後に特徴的でユニークな現代語訳3つを紹介しよう。 『大塚ひかり全訳 源氏物語』(ちくま文庫) 『源氏の男はみんなサイテー』『カラダで感じる源氏物語』(ともにちくま文庫)などの傑作古典エッセイで知られる大塚ひかりの全訳版。長年、原文に親しんできた大塚は「古典は原文を読むべき。だから私は現代語訳は基本的に読まない」と発言しているが、そんな彼女自身が「欲しかった逐語全訳」なのだという。 筑摩書房のホームページによると、「原文を重視し、原文のリズムを極力重んじ、また『要注目』の原文はそのまま本文に取り込みつつ、『するする分かる』訳」とある。 また、随所に「ひかりナビ」というコラムを差しはさみ、、読み取るべき「ツボ」がわかりやすく解説されているという。 『A・ウェイリー版 源氏物語』(左右社) 近代に入って初めて源氏の現代語訳をしたのは、与謝野晶子だが、それに続くのは谷崎潤一郎ではなく、イギリス人の東洋学者アーサー・ウェイリーだった。それが『The Tale of Genji』で、完成したのは1933(昭和8)年のこと。英米で紹介されるやたちまちベストセラーになり、「文学において時として起こる奇跡のひとつ」「疑いもなく最高の文学」と絶賛されたという。 本書は、そのウェイリー版の現代語訳を毬矢まりえ+森山恵姉妹がさらに日本語に訳した逆輸入版。光源氏が「ゲンジ」「シャイニング・プリンス」とカタカナ表記される、ちょっと不思議な世界である。90歳をこえる瀬戸内寂聴も、第一巻を徹夜で読了し、その後も丁寧に読み直したという。非常に興味がそそられる現代語訳である。 角田光代訳『源氏物語』 河出書房新社より出版された『池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』に収められた源氏の現代語訳を手掛けたのは、売れっ子小説家の角田光代。日本人が手掛けた現代語訳は、原稿用紙4000枚を超える大著だったが、この角田版はコンパクトにまとまっていて、「イッキ読み」にふさわしいものになっている。河出書房新社の公式ホームページによると、角田版には次のような特徴があるという。 原文に忠実に沿いながらも現代的で歯切れがよく、心の襞に入り込む自然な訳文 地の文の敬語をほぼ廃したことで細部まで分かりやすい 生き生きとした会話文 草子地(そうしじ)の文と呼ばれる第三者の声を魅力的に訳して挿入 和歌や漢詩などの引用は全文を補って紹介 さて、『源氏物語』の現代語訳について、できるだけ網羅的に紹介してきたつもりだが、私自身、「読了したのがまだ一冊」という超初心者である。 できれば今後、原文にも触れながら、2種類、3種類と別の現代語訳に触れて、「源氏好き」を公然と名乗れるほどになっていたい。そうなれば、大河ドラマ『光る君へ』が放送されている2024年は、秘かな優越感に浸りながら過ごせるはずだ。
2023/04/21

『悪意の科学』─「誰もが持っている意地悪な心を自制する方法」に効く1冊
「悪意」は一般的に、「他人に害を与えようとする心」と理解されている。つまり、普段は自制していなければならない心、片隅にしまっておかねばならない心なのだが、人間関係やビジネス、宗教間、SNSなどでのやりとりを見てみると、「悪意」はむしろ、ありきたりなものとして存在している。なぜだ? 進化論的に見ても、これはおかしい。嫌がらせや意地悪といった悪意ある行為は、他人に害をおよぼすのだから、自然選択の力がはたらいて淘汰されるはずである。どういうことなんだ? 本書は、そんな疑問を出発点にして、悪意を行動経済学、心理学、遺伝学、脳科学、ゲーム理論など、さまざまな視点から分析していく。悪意とは何か? 悪意をコントロールする術はあるのか? そのスリリングな問いをレビューしていこう。 『悪意の科学 意地悪な行動はなぜ進化し社会を動かしているのか? 』 著者:サイモン・マッカーシー=ジョーンズ/著、プレシ南日子/訳 発行:インターシフト 定価:2200円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ 死角にあった悪意をあぶりだす「最後通牒ゲーム」とは? まずは本書において、スルメを噛むかのように繰り返し語られる「最後通牒ゲーム」という心理実験を紹介しよう。 このゲームは、隣の部屋にいる相手とペアになってプレイする。プレイヤーのひとりは、10ドルほどのお金を与えられ、「このお金を隣の部屋にいる相手と分けあってください」と指示される。そして、もう一方のプレイヤーは、こんなルールを説明される。 「隣の部屋にいる人は10ドル持っていて、あなたと分けあうことになっています。そのとき、あなたにはお金を受けとることを拒否するという選択肢があります。拒否したら、あなただけでなく、相手の人もお金はもらえなくなります。ゲームをプレイするのは1回だけなので、その選択が最後通牒になります」と。 そのお金は、人生ゲームやモノポリーなどで使うゲーム用のニセ金ではない。日本円に換金すれば、だいたい1300円になる正真正銘の現ナマである。 お金の価値をわかっている人なら、隣の部屋の相手が不公平な配分をしても、「受け取りを拒否する」という選択はしにくいだろう。例えば、相手が2ドルを寄こしてきた場合、「自分より6ドルも余計にもらうのかよ」とイラッとはするかもしれないが、2ドルは確実に自分の手元に残るのだから。 ところが結果は、その予想を裏切るものだった。10ドル中2ドル以下の配分に対して、受け取りを拒否した人が50%に及んだというのだ。つまり、半数の人が1~2ドルを捨て、自分より儲けようとする相手への悪意を発動させてゲームをご破算にしたのだ。 日本には「肉を斬らせて骨を断つ」というサムライ由来の言葉があるが、どうやらこれは日本オリジナルではないようだ。 このゲームを考えたのは、ドイツ・ケルン大学教授の33歳の経済学者のヴェルナー・ギュートらの研究チーム。彼は子どもの頃、ひとつのケーキを兄弟と分けあうとき、ナイフの当て方に対していつもいちゃもんがついたという経験から着想したのだという。 悪意を剥きだしにした被験者に対してギュートは、どのように実験結果を報告したのだろう。本書はそのことに触れていないが、「相手に罰を与えるために自分も損するなんて、君はなんて大人気ないんだ」などと言っていたとしたら、被験者はさらにイラくか、赤面したのではないか。そういう意味では、かなり意地悪な実験である。 だが、1977年にギュートが報告したこの論文が発表されると、たちまち多くの研究者が自分の論文に引用したばかりか、以後、さまざまな工夫をこらして再実験をアレンジしたそうだ。 悪意を持つか持たないかは「人間の証明」にかかわる問題 アメリカの経済学者のエリザベス・ホフマンらは「最後通牒ゲーム」の結果が、金額が低いためにそうなったのではないかと考えた。1~2ドルほどのはした金なら、もらえなくても大した損にはならない。ならばそれより、不公平な配分をした相手を懲らしめるほうに使ったほうがいいと判断したのではないかと。 そこでホフマンらは、5000ドルの予算をつぎ込んで再実験を設定した。各ゲームにおいて、被験者たちが現金100ドルを分けあうことにしたのだ。 その結果、低額オファーに悪意を発動した人の数はさらに増えた。なんと、100ドル中10ドルの配分をした相手のオファーを75%が拒否し、さらに100ドル中30ドルのオファーに対しても50%が拒否したという。 さらにインドネシアでおこなわれた「最後通牒ゲーム」は、ホフマンの実験よりも規模が大きく、被験者には平均的な学生が1ヵ月に使う金額の3倍のお金が渡された。 相手の配分が20~30%だったとしても、1ヵ月弱の生活費が浮くのだから拒否する人は少なくなるはずだ。実際、その通りになったが、それでも10人に1人がその大金の受けとりを拒否したのだという。人は、悪意に大金をつぎ込む生き物なのだ。なんて罪深い存在なんだ。なんて残酷な実験なんだ! 1995年には、人類学者のジョセフ・ヘンリックが社会の違いに着目して再実験をした。ヘンリックはペルーを訪れ、マチュピチュ遺跡の近くで暮らすマチゲンカ族という先住民を被験者にして「最後通牒ゲーム」をおこなった。すると、20%以下の低額オファーを受けた10人のうち、それを拒否したのは1人だけだった。つまり、マチゲンカ族の人たちは、タダでもらえるお金を拒否するなんてばかげていると判断できる現実主義者だったのだ。 かつて私は、奥野克巳『これからの時代を生き抜くための文化人類学入門』(辰巳出版)のレビューをしたが 、そこではボルネオ島の狩猟民プナンの人たちがお互いの所有物を惜しげもなく分け与えている暮らしが紹介されていた。従って、ヘンリックの検証結果には、さもありなんと大いにうなずくことができる。 ちなみに、チンパンジーに「最後通牒ゲーム」に似た実験をした例があるそうだが、低額オファー(ここではお金ではなくバナナ)を拒否したチンパンジーは1頭もいなかったという。どうやら悪意があるかないかは、「人間の証明」にもかかわってくるらしい。 トランプ大統領の登場もイギリスのEU離脱も、国民の悪意が政治を動かした結果である 本書は、前半部を通じて「最後通牒ゲーム」のさまざまなバリエーションを紹介しているが、主眼はそこだけにはない。人間の悪意が、実際に現実社会の政治や宗教に影響を与えた事例を分析する後半部で、その内容はさらに説得力を増していく。言うなれば、前半部は基礎研究の紹介で、後半部はその応用を展開しているのだ。 著者のサイモン氏が最初に選んだ事例が、2016年のアメリカの大統領選挙だ。当初、圧倒的に有利と見られていた民主党候補のヒラリー・クリントンが、エキセントリックな問題児として知られる共和党候補のドナルド・トランプに破れた珍事である。 その原因について、アメリカから遠く離れたアイルランド・ダブリン大学の准教授のサイモン氏は次のように述べている。引用しよう。 アメリカ政治を外から見ると、2016年の大統領選はまるで罰を与えるための選挙のようだった。投票所を訪れた有権者は「誰を支持しよう?」というより、「誰を傷付けよう?」と考えていたと思われても仕方がない。こうした罰はしばしばヒラリー・クリントンに向けられた。 選挙戦中、ヒラリーが「私は家にいてクッキーを焼いてお茶を飲んでいることもできましたが、自分の職業を全うすることを選びました」という発言が、米国初の女性大統領の誕生を望む女性たちの票を失ったことは有名だが、その他にも数々の要素がはたらいて、ヒラリーはアメリカ国民の多くを見下す、セレブで傲慢な人物という印象が形成されていった。 予備選でヒラリーといい勝負をしてきたバーニー・サンダースは敗戦後、民主党の勢力維持のために自らの支持者にヒラリーへの投票を呼びかけなければならなかったが、選挙戦で「どちらが公平か? 不公平か?」というキャンペーンを張っていただけに説得力のある弁護ができなかった。 そのため、「最後通牒のゲーム」の法則でいえば、サンダースを支持していた多くの人は「選挙に行かずに票を減らす」という低リスクの罰をヒラリーに与えるか、あるいはメキシコとの国境に壁を作るといったトンデモ政策を打ち出している「トランプに投票する」という高リスクの投票行動に走った。 実際、この高リスクに掛け金を投じた人の多くはトランプの大統領就任後、「ベットに失敗した!」と、覚ったはずだ。もともとヒラリー支持者だった人々にとって、トランプへの投票は自傷行為だったのだ。 くわしい経緯については、本書を読んでいただくとして、有力候補と見られていた初の女性大統領の誕生を阻んだ原因がアメリカ国民の「悪意」のみにあるとは言わないまでも、多くの要因において、それが示された疑いようのない証拠が本書には並べられている。 国民の悪意が政治を動かしたもうひとつの事例として紹介されるのは、先に述べたアメリカ大統領選と同年の2016年におこなわれた、イギリスのEU離脱の是非を問う国民投票である。この投票では、52%の国民が離脱に賛成票を投じたことは、記憶に新しい。 投票に向けたキャンペーンでは、離脱が多大な経済的コスト負担につながることを多くの人が訴えた。保守党のデイヴィッド・キャメロン首相は、EUの離脱は「イギリス経済の真下に爆弾を仕掛ける」ことになると主張した。スコットランド独立を訴え続けているスコットランド国民党のニコラ・スタージョンも「悪意から自分の損になることをしてはいけません。不満や怒りに駆られて未来を決定しないでください」と訴えた。 にもかかわらず、52%の賛成票が集まったのは、当時のイギリス社会に「EUは不公平だ」という強固な世論が形成されていたからだ。そして、それに対する抗議の賛成票がかなりのコストをともなうことが再三にわたって告知されたものの、半数以上の国民が自分をも傷つける可能性のある悪意を発動させたのだ。 SNS中では、人間の悪意は自由に動きまわる 本書はこのあと、宗教に目をつけて9.11の自爆テロの論理に言及していくが、デリケートな話なのでここでの紹介は避けておこう。私が興味をかきたてられたのは、インターネットのなかでの悪意のふるまいだ。 ソーシャルネットワークは悪意のコストを減らし、利益を倍増させる。ソーシャルメディアは悪意がはびこる最悪の状況を生み出すのだ。現実世界には悪意を抑えるブレーキが存在するが、オンラインの匿名性はこの必要不可欠なブレーキを外してしまう。そして、報復の脅威を消し去る。報復の不安から解放された人々は、自分たちよりも地位が高い、または豊かな人々にためらうことなく反支配的悪意を向ける。そして、熱狂的に正義を訴え、ほかの人々を傷付け、破壊の喜びにひたる。ターゲットにされる人々が努力によって利益を得たかどうかは関係ない。有能なおかげで出世した人は、さらに嫌われるのだ。 いやはや、恐ろしい世の中になったものだ。 本書はこうした悪意を自制し、コントロールする手段として瞑想などの方法を提案しているが、あまり説得力を感じなかった。それよりむしろ、本書の読者が本を読んだあとに自らの胸に手を当てて、どれほどの悪意が心の中にあるかを考えることが、もっとも最善の方法なのではないかと思った。
2023/04/14

『父を焼く』─「老いの悲惨さのなかに表れる希望」に効く1冊
『父を焼く』というショッキングな題名の漫画を読んだ。 だが、冷静になって考えてみれば、親を亡くした者はすべて、「父(母)を焼く」という経験を有しているものだ。かく言う私もそうだった。 作画を手掛けた山本おさむ氏は、ろう学校を舞台に描いた名作漫画『どんぐりの家』で知られる人間ドラマの名手である。ずっしりと重い読後感を受けとめつつ、この作品をレビューしていこう。 『父を焼く』 著者:山本おさむ/画 宮部喜光/原作 発行:小学館 定価:1170円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ 孤独死した父を野辺送りする息子の話 まずは、この漫画のストーリーの背景を紹介しよう。 主人公の三上義明は、55歳。家電量販店で働きながら、夫婦共稼ぎでひとり娘を大学に行かせ、就職してひとり立ちをさせたばかり。それを機に、彼は自らの老後を意識するとともに23年前、突然孤独死した父・義雄のことを回想する。 父の義雄は不運の人だった。高校をいちばんの成績で卒業して馬の獣医師資格を得るも、戦争が終わって軍馬の必要がなくなり、職を得ることができなかった。この最初のつまづきが尾を引くかのようにして「恋人の自殺」「左目の失明」「結婚後、最初の子を1カ月で亡くす」という不幸にみまわれる。 その結果、義雄はアルコールに逃げるようになり、第2子の義明が産まれて以後、まともな定職につかずに妻に暴力をふるうDV男になってしまった。そうした事情から義明は、高校を卒業してすぐに故郷の岩手県を逃げるように去って上京したのだ。 だが、それで親子の縁が完全に断ち切れたわけではない。 例えば家電量販店の契約社員となって1年目、義明が住む風呂なしの四畳半アパートに岩手県F市の生活福祉課の女性が訪ねてくる場面がある。 両親が生活保護を受けることになり、彼に金銭的な援助ができるかどうかの確認をする必要があるという。民法では直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養をする義務がある旨が定められていて、義明は毎月10キロの米を実家に送ることを約束させられる。 そんな義明が父の孤独死の報せを受けたのは、33歳のとき。すでに母親は糖尿病を悪くして2年前に亡くなっており、ひとり暮らしをしていた父の義雄は、自宅の寝床で死後数日経って腐乱した状態で発見された。 その布団にはおびただしい数のハエがたかり、ミイラのように包帯が巻かれた遺体にはウジが湧いていた。そのグロテスクな描写は、「漫画」という形でしか表現できないリアルさで誌面に迫ってくる。 そして物語は、三上親子の壮絶な出来事を回想しながら、55歳になった義明が23年間、自宅アパートの天袋に保管していた両親の骨壺を樹木葬で合祀するところで終わる。 シニア読者を意識した新レーベルの誕生 読後感は、決してスッキリするものではない。特に、主人公の義明と「30代前半で父と死別」「現在、50代なかば」「大学を卒業した我が子がひとり立ちしたばかり」という共通の経験を持つ私にとって、身につまされる話だった。 だが、老後のとば口に入って、自らの「死」について思いを巡らす心境については、共感させられた。そして、最後の最後で語られる「今が血反吐を吐くような厳しい時代だという事は分かっている。でも俺達は悲観せず生き抜こうと思う」という義明の決意には大いに励まされた。 ちなみにこの『父を焼く』は、小学館の「ビッグコミックス」の新レーベル「ビッグコミックス フロントライン」から発表された第1段の作品で、今後も老い、介護、看取り、終活、終の棲家といった題材を扱った作品をコミックス化していくという。 すでに第2弾となる齋藤なずな『ぼっち死の館』と、第3弾の山本おさむによる『もものこと 愛犬と老人の最期の日々』が出版されている。 「ビッグコミックス」は30代以上の男性をターゲットにした「青年誌」だが、そのような呼称ではシニア層に届けきらない時代になってきたことを受けて、70代以上の読者に向けて創設したレーベルだという。 「ビッグコミックス」というと、30代に熱心な読者だった私は、弘兼憲史の『黄昏流星群』の連載が始まったときに「あれ?」と思った記憶がある。「青年誌なのに、なぜシニア向けの漫画を始めるのか」と。 調べてみると、『黄昏流星群』が最初に掲載されたのは1995年の11月。今から28年前の話である。だが、今思えば「ビッグコミックス」は、そんな昔から「シニア」の読者を想定していたということになる。 1995年というと、総人口に対する65歳以上の人口割合(高齢化率)が14%を超えて14.6%になった年である。昨年2022年には、これがほぼ2倍の29.1%になった。 当時、「日本ではやがて、全人口の3人に1人が65歳以上になる」という新聞記事を読んで、「その3人に1人の老人って、オレら世代のことじゃねぇか!」と驚いたことをよく覚えている。 「ビッグコミックス フロントライン」のようなシニアレーベルの登場は、必然の流れだったのだ。 貧しく孤独な日々をおくる老人のリアル というわけで、シリーズ第3段にあたる『もものこと 愛犬と老人の最期の日々』のほうも気になって読んでみた。 主人公の刈田有三は81歳。かつかつの年金で生活をするなか、「肺がんで余命1年」と医師に告げられる。そのとき彼の脳裏を貫いたのは、それまで心のやすらぎを与えてくれた愛犬もものこと。 すでに妻を亡くし、天涯孤独の身になっていた刈田には、里親になってくれそうな人脈もない。NPO法人を訪ねて里親募集をしてもらうが、12歳の高齢犬はもらい手が少なく、「あまり過剰な期待はなさらないように」とクギを刺されてしまう。 いよいよ病状が悪化し、救急車で病院に運ばれた刈田は、病院を抜けだして置去りにされた愛犬を探しに行くのだが……。 という具合に、こちらも『父を焼く』と同様、貧しく孤独な日々をおくる老人のリアルな日常が描かれる。だが、物語は病院のエピソードをきっかけにして、思わぬ人物との出会いが彼を窮状から救う形で展開していく。 そうなのだ。この作品もまた、「老い」の悲惨さを描くだけでなく、その悲惨さに向き合い、懸命に生きようとする主人公の奮闘ぶりとその希望を描くことに主眼が置かれているのである。 今回、この2冊の漫画を読んだことで、「ビッグコミックス フロントライン」という異色の新レーベルから、シニア市場を賑わすヒット作がいつしか生まれるのではないかという予感を確かにした。 『もものこと 愛犬と老人の最期の日々』 著者:山本おさむ/画 宮部喜光/原作 発行:小学館 ...
2023/04/07

『なぜ、人は病気になるのか?』─「すべての病の根本原因から治療し、“未病”に至る道」に効く1冊
なぜ、人は病気になるのか? バカのふりして聞いたところで、この質問に明確な答えを持っている人は、病気の専門家の医師でさえいないだろう。 だがもし、その疑問に対する明確な答えがあるとすれば、人は病気にならずに済むことになる。なぜなら、「病気はこういう原因で起こる」ということがわかれば、その原因をなくすことで人は病気にならずに安心して暮らしていけるからである。 ありがたいことに本書は、医師である寺田武史氏が全身全霊をかけて病気の「根本原因」を探り、そのメカニズムをくわしく解説してくれる本なのである。 病気を未然に防ぐために今、知っておかねばならないこととは? その貴重な知見の一部をレビューしていこう。 『なぜ、人は病気になるのか?』 著者:寺田武史 発行:クロスメディア・パブリッシング 定価:1580円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ 「病気」と「病気でない」の間にはグラデーションがある 著者の寺田武史氏は、消化器外科医として10年間、大学病院に勤務してがんの手術を手掛けていた医師。その後、大学病院を離れ、開業医をしていた父のクリニックを引き継ぐ形で開業医になったという。 外科医だったころの寺田氏は「外科医こそが患者さんの命を救う」と使命感を持っていたそうだが、最新、最善、最良の手術、治療をしたのに病気を繰り返してしまう患者をみているうちに、だんだんと失意を感じるようになったという。 その失意が「なぜ、人は病気になるのか?」という問いに寺田氏を向かわせた。 予防医学などの文献や論文をむさぼり読み、玄米菜食、ファスティング(断食)、低糖質タンパク食、ビーガン食など、健康に良さそうなものを実践しながらたどりついたのが、分子栄養学という学問だったという。 そこで寺田氏は、次のような結論に達する。引用しよう。 現代医学の基礎理論である西洋医学の世界では、端的にいうと「正常」と「異常」の2つの概念しかありません。たとえ目の前の患者さんが辛い症状を訴えていたとしても、検査データや画像の所見で異常がなければ「あなたは正常です」ということになります。ただ、現実には画像でも数値でもとらえられない「異常」があるものです。「病気」と「病気でない」の間には明確な境界線があるのではなく、グラデーションで連続的につながっています。 その中間点を「未病」といい、そこから「病気」に至る道を断ってしまえば、人は病気を克服することができる。寺田氏の考えをシンプルに説明すれば、そういうことになる。 病気はズバリ、「副腎疲労」から来る では、「未病」はどうして「病気」に至るのか? 寺田氏はズバリ、「副腎疲労」が原因であると断言する。 副腎とは、腎臓の上に位置する直径3センチほどの三角形の臓器だが、さまざまなホルモンを分泌し、心身のバランスを維持しているという。 なかでも重要なのが「コルチゾール」というストレスホルモンで、血糖を上昇させる、筋肉中のタンパク質の分解を促進させる、脂肪組織で脂肪の分解を促進させる、炎症を抑えて免疫のはたらきを抑制する、1日の活動リズムを整えるといった重要な働きをしている。 で、このコルチゾールの供給バランスが乱れるとき、「未病」は「病気」に至るのだという。 わかりやすい。非常に明確な説明だ。寺田氏はさらに、このコルチゾールの乱れが起こる根本原因を次の5つに断定している。 慢性炎症 低血糖 睡眠不足 ストレス 運動不足 この5つの根本原因から治療してしまえば、「病気」はつねに「未病」のままでいられるのだ。 5つの根本原因に対処すれば病気は必ず防げる 根本原因のひとつ目の「慢性炎症」について、寺田氏は次のように説明している。 炎症は、身体の機能としてなくてはならないものです。知覚できる発熱や痛みがあることで、私たちは初めて身体の不調を感じることができます。炎症は、身体の不調を伝えるサインなのです。しかし、それらの急性炎症が鎮まっているにもかかわらず、私たちの体の中では、知覚できないレベルで炎症がずっと起こり続けていることがあります。じわじわと炎症を繰り返しているうちに、知らない間に体の不調が進行していくのです。これが「慢性炎症」といわれるものです。 そして「慢性炎症」は、具体的には上喉頭炎、歯周病、脂肪肝、腸内環境の乱れ、肥満、うつ、老化、不眠など、実に幅広い症状をもたらすのだという。 持続する炎症を止めるには、ブレーキ役となる栄養素、具体的にはエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)といった抗炎症性脂質や、ベルビリン、ケルセチン、クルクミンといった抗炎症性ハーブ、そしてビタミンDを摂取することが有効だ。 次にふたつ目の根本原因である「低血糖」は、すべての病気の根源といってもいいくらい、病気のリスクが高い症状だと寺田氏は指摘する。 膵臓(すいぞう)の老化や肥満などによってインスリンを分泌する能力が衰えると、食後に血糖値が乱高下する「血糖値スパイク」が起こる。 インスリンの分泌量が減ったり、分泌するタイミングが遅くなったりして血糖値が激しく上下するのだが、これをコルチゾールやアドレナリンを分泌して安定させようとするのが先に述べた「副腎」だ。血糖値スパイクは、5つの根本原因の元となる「副腎疲労」に直結する。 また、低血糖はミトコンドリアの機能障害の原因にもつながっている。ミトコンドリアは人体を形成している約37兆個の細胞のなかにある細胞小器官のひとつで、「アデノシン三リン酸(ATP)」という高エネルギー物質を産生していて、寺田氏によれば、人間の生命維持に欠かせない「エネルギー産生工場」なのだという。 ミトコンドリアの機能障害によって起こる症状は、実に幅広い。 疲れやすい。風邪をひきやすい。むくみがある。便秘や下痢。吐き気。食欲不振。動悸・息切れ。頭痛。冷え性。月経異常。神経過敏。イライラ。髪が抜けやすい。立ちくらみ。めまい。肩こり。腰痛。背中の痛み。などなど…。 これらの症状は、医学的には「不定愁訴」と呼ばれるものだが、誰もが何度も経験していることなのではないか。 病気の根本原因の後半3つ、「睡眠不足」「ストレス」「運動不足」についてはわかりやすい自覚症状があるので、多くの人がその弊害に気づいているだろう。 本書ではその弊害を、身体の機能を詳しく説明しながら理屈立てていく。 「睡眠不足は慢性炎症を引き起こし、インスリン抵抗性があがって糖尿病リスクを高める」とか、「ストレスは脳のエネルギー(ATP)消費を高めてミトコンドリア機能障害につながる」とか、「運動はインスリン抵抗性を改善し、ミトコンドリアを増やし、自律神経のバランスを整えるはたらきがある」などと説明されると、ウンウンとうなずきながら納得するしかない。 特に、これらの説明が「慢性炎症」「インスリン抵抗性」「ATP」「ミトコンドリア」といった共通のキーワードでからみ合っているところが興味深かった。 なぜ病気になるのか?という疑問に全力でぶつかった寺田氏に感謝! さて、5つの「根本原因」を防ぐ手段として、寺田氏が推奨しているのは「腸内環境を整える」ということと、「肝臓デトックス」だ。 腸の働きについて、寺田氏はこう説明している。 実は、腸は「第二の脳」とも呼ばれ、独自の神経ネットワークを持っており、脳からの指令がなくても独立して活動することができます。脳からのシグナルを待つことなく、消化・吸収や排泄といった機能を果たしています。また、近年の研究では、脳と腸が互いに情報を伝達し合い、双方向で作用しあう関係にあることがわかってきました。人間にとって重要な2つの臓器、脳と腸が密接に影響を及ぼしあうことを「腸脳関係」といいます。 そして、腸内環境を改善する方法として、寺田氏は「アルコールやカフェイン、精製糖質、精製穀物(小麦粉/グルテン)などを過剰に摂取しない」「化学物質、排気ガス、タバコ、食品添加物などの毒素を身体に入れない」「精神的ストレスをためない」などの方法を提案している。 次に「肝臓デトックス(解毒)」は、腸内環境と連携しながら病気を防ぐ「最後の砦」だと寺田氏は指摘する。 肝臓は、有害物質を解毒するだけでなく、脂質代謝や糖代謝、免疫のコントロールなどに欠かせない胆汁酸を産生し、低血糖を抑えるエネルギー代謝機能を持っているからだ。 最終章のタイトルは、「『5つの根本原因』は食事から予防・改善しよう」となっていて、「運動」「睡眠」の改善とともに「食事」の3本柱を掲げて病気を防ぐ方法を説明している。 その内容は実際に本書を読んでいただくとして、最後に「あとがき」で述べている寺田氏の説明を紹介しよう。 もう一度お話させていただければ、私は、アトピー性皮膚炎も、甲状腺機能低下症も、過敏性腸症候群も、線維筋痛症も、頭痛も、風邪も、うつも、ADHDも、自閉症も、そしてがんも、病気の原因は「慢性炎症」「腸内環境の乱れ」そして「デトックス機能の低下」の3つと考えています。そして、その慢性炎症を引き起こすものが「運動不足」であり、「ストレス」であり、「睡眠不足」で、もちろん感染症も忘れてはいけません。そもそも食生活が乱れていれば血糖のコントロールはうまくいかず、「低血糖」を引き起こします。全ての「病気」はこの5つの根本原因から始まるのです。 寺田氏が医師として、このようなことを語るのは、実は大変な勇気を要したのではないか? 「なぜ、人は病気になるのか?」という問いへの模範解答は何かといえば、「医者は病気を治療するのが仕事ですから、そんな質問に答える義務はありません」と多くの医師が答えるだろう。 その意味でわれわれ読者は、寺田氏の言い出しっぺの決断に、最大限の感謝を捧げなければならないのではないか。
2023/03/31

【コラムニスト・泉麻人】昔の記憶を旅する「時代トリップ」は、年齢を重ねた人ならではの愉しみ
銀座は表通りの広々とした歩道を散歩するのもいいけれど、ちょっと横道にそれるとホッとする。西五番街、みゆき通り、交詢社通り、タテヨコの静かな道を歩いていると、なんとなく銀座の通人になった気分になれるものだ」 泉麻人さんの近著『銀ぶら百年』(文藝春秋)からの一節だ。 これまで「東京」をテーマにした本を多く書いてきた泉さんだが、銀座というひとつの町にテーマを限定した本は、これが初めてだという。 そこで今回は、街歩きの愉しみについて語っていただきながら、今年の4月で67歳になる「老いの心境」についてもじっくり話を聞いていこう。 『銀ぶら百年』 著者:泉麻人 発行:文藝春秋 定価:2000円(税別) 80年代の東京には、イジリ甲斐のある個性があった ―『銀ぶら百年』(文藝春秋)のあとがきで泉さんは「『東京』と銘打った本は、これまでいくつも書いてきた(20冊くらいはあるのではないか?)」と書いています。そんな泉さんにとって、東京とはどんな存在なのでしょう? 生まれ育ったのが新宿区の端っこの落合というところで、子どもの頃から東京の地図を見て細かいところを調べたり、知っているバス停を書き入れたりするのが好きでした。小学生の低学年の頃は、自転車で行ける範囲を探検してましたけど、学年が上がっていくとバスとか地下鉄といった公共交通機関を使っていろいろ行くようになりました。よく覚えているのが1969年、中1の夏に都営三田線の巣鴨と志村(その後、高島平に改名)の間が開通して、初日を狙って乗りに行ったことです。高島平団地はまだできてなくて、駅を降りると田んぼをつぶして造成した、だだっ広い土地が広がっていて、成増あたりの丘が見えたのを覚えています。 ―そのような趣味を活かして東京についての文章を書き始めたのは、いつ頃ですか? 1980年くらいに流行通信社(現・INFASパブリケーションズ)の「スタジオボイス」という雑誌に泉麻人というペンネームを使って初めて書いたのが東京についての文章だったし、マガジンハウスの「POPEYE」では、後に本にもなった『街のオキテ』(新潮文庫)という企画を連載しました。1回目のネタが、「東京23区の偉い順」というランキング遊び。そのほか、「喫茶店でウンコをした場合の正しい言い訳」とか「ゲロのカッコイイ吐き方」と、モヤモヤとした街の約束事について書いていくうちに主婦の友社の編集者が声をかけてくれて『東京23区物語』を書くことになりました。 ―『東京23区物語』は1985年に単行本になって、その16年後の2001年には改訂版となる『新・東京23区物語』(ともに新潮文庫)を書くことになりますね。 最初の本を書いた頃は、日本がまだ景気のよかった時代で東京自体、地域によっていろんな個性を持ってました。そこで「隅田川をわたると住民のパンチパーマ占有率が高くなる」とか、「練馬、杉並、中野は水原弘・由美かおる看板の残存率が高い」なんて、その違いをちゃかして書いたんです。ところが、2001年にその新版を書いた頃は東京の平板化が進んでいて、以前のような個性が薄れていました。僕自身、ギャグっぽい文章を書くのに飽きていたこともあるけど、新版では東京の変化をマジメに記録しようという意識で書いた覚えがあります。その後、自転車に乗って東京を探訪した『東京自転車日記』(新潮文庫)、路線バスの乗り歩きエッセー『大東京バス案内』(講談社文庫)、知る人ぞ知る宿に泊まって町歩きを愉しむ『東京ディープな宿』(中公文庫)、喫茶店探しにポイントを置いた『東京ふつうの喫茶店』(平凡社)、七福神巡りに特化した『東京・七福神の町あるき』(淡交社)と、手を変え品を変えて東京についての本を書いてきました。 僕にとって銀座は「近くて遠い都会」だった ―『銀ぶら百年』(文藝春秋)もそうした東京本のひとつだと思いますが、ひとつの街をテーマにした本は初めてだったそうですね? 銀座の商店会が中心となって運営している「GINZA OFFICIAL」というWebサイトに書いた連載コラムが元になっているのでそうなったんですけどね。「銀ぶら」という言葉が生まれたといわれている大正4、5年から現在に至る約100年の歴史をふまえつつ、銀座の魅力を再考する内容にしてほしい、といわれても、銀座は数えきれないほどの老舗がある街だし、これを網羅的に取りあげるのはむずかしい。そこで、銀座のなかでも自分との関わりのある店やスポットから取りあげていくことにしました。 ―泉さんが最初に銀座と関わりをもったのは、いつ頃なんでしょう? 幼稚園児の頃、母に連れられて銀座のデパートに買い物に来たとき、数寄屋橋の不二家でプリンやチョコレートパフェなんかをおねだりして食べた思い出が強く残っていますね。買い物といっても、ショッピングだけが目的なんじゃなくて、「銀座に行く」こと自体が今思えば一種の娯楽のようなものでした。というのも、僕みたいな山手線の外側の落合という場所に住んでいる者にとって、銀座という街には「近くて遠い都会」というイメージがあったんです。地下鉄に乗れば30~40分くらいで着いてしまうんだけど、駅から降りて見た都会の風景はまったくの別世界。「ビル」と呼ばれる建物がザーッと並んでいる街並みは、落合界隈では絶対に見られない景色でした。 ―銀座が今でいう、テーマパークのように見えていたんですね。 実際、銀座には生まれて初めて見るものがあふれていました。今、ティファニー銀座本店がある場所にはかつて、「オリンピック」という洋食レストランがあって、店の片隅に見たこともないような大きなオーブンがありました。母はこれを日本式に天火(てんぴ)と呼んでましたけど、そこに皿ごと入れて焼いたアツアツのマカロニグラタンの焦げ皮の味は忘れられないものがあります。そういう記憶のなかの空気感を足掛かりにして、銀座の魅力をひもといていこうとしたわけです。 衝撃的な出会い!マクドナルドのハンバーガー ―中学生になって、慶應義塾中等部に進学した泉さんにとって、銀座は学校帰りの寄り道スポットになるわけですよね? そうですね。慶應の中等部というのは、前身が商工学校だったこともあって、人形町や浅草で商店を営む家に生まれた子が多かったんです。僕はサッカー部に入っていたんだけど、チームメイトにはカバン屋さん、靴屋さん、ハンカチ屋さんの子がいました。で、そういう下町育ちの子は、出入りの職人さんから小遣いをもらっていたりして日銭を持っているので、買い食いにも慣れているんです。1971年に銀座三越の1階に開業したマクドナルドに行っても、平気な顔でビッグマックなんかを食べているわけ。 ―1971年というと、泉さんが中学3年生のときですね。 当時の僕にとってハンバーガーは、未知の食べ物でした。たまに三笠会館などのレストランに連れていってもらったとき、普通に作ったハンバーグをパンではさんだ分厚いサンドイッチ風のものを見たことはあったんだけど、アメコミの『ポパイ』でウィンピーおじさんが食べているハンバーガーとはほど遠いものでした。だから、マクドナルドに行って初めてハンバーガーを見たときは強い印象を受けました。薄いバンズにはさまれていて、なるほど、こんなにおいしいものならウィンピーおじさんが好物にするのも納得できるなと、腑に落ちました。 ―日本初出店のマクドナルドは、日本人にハンバーガーの味を知らしめた存在だったんですね。 ハンバーガーのほかには、シェイクも衝撃的でした。ジュースともアイスクリームとも違う、太いストローを挿して思いきり吸い込む、新しいスタイルの飲み物。ちなみに、マクドナルドが開店した前年の1970年は銀座を始めとする繁華街で「歩行者天国」が始まった年でもあるんですが、いつもはクルマが通っている道路を友だち連中と歩きながら、マックシェイクの早飲み競争をしたものです。歩行者天国といえば、マクドナルドが開店した同年に日清食品がカップヌードルの実演販売をした場所としても有名です。当時の銀座は、それまで日本になかった新商品の市場調査をするマーケティングの場でもあったんですね。 「変わっていく」ことそのものが東京の特色 ―その後は、どんな風に銀座と関わりを持っていったのですか? 高校時代は、銀座に行った記憶はそんなにないんだけど、大学時代の後半には「コピーライター養成講座」の夜間コースに週1~2回ほど通い始めて、その会場が銀座2丁目にある横長の中小企業会館ビルにありました。その後、東京ニュース通信社に就職して『週刊TVガイド』の記者になってからは、社屋が築地にあったので銀座は近い存在でしたね。それから、会社に内緒でライターの副業をやるようになってからは、東銀座のマガジンハウスにも足繁く通うようになりました。当時、駆け出しのライターにはFAXで原稿を送ることなんか許されていなくて、編集者に原稿を手渡ししていたんです。東銀座の周辺にはまだ老舗旅館がいくつも残っていて、そこの大広間を貸し切って編集者とライターが特集の記事づくりをしたりしていました。こうしてふり返ってみると、僕は人生のいろいろな場面で銀座と関わってきたことになりますね。 ―『銀ぶら百年』で紹介されたお店のなかには、本の出版後に閉店してしまったお店がありますね。 アイビールックの牽引役だった「テイメン(テイジンメンズショップ)」が、本の発売から2カ月後に閉店してしまったのにはショックを受けましたね。それから、銀座4丁目交差点で「和光」と並んでシンボリックな建物だった「三愛」の円筒形ビルも今朝(2023年3月14日)の新聞を読んでいたら老朽化で建て壊しになるという記事が載ってました。本で紹介したときは、婦人服の三愛はすでに撤退していて、創業者の会社のリコーの歴代カメラが展示されている様子を書きました。ビルは銀座のランドマークとして残されていくんだろうな思っていたけど、なくなっちゃうんだね。 ―そのように銀座が、東京が、めまぐるしく変わっていくことについて、泉さんはどう思っていますか? ヨーロッパだと、100年以上も経つ建物が普通に立ちならんでいる街が当たり前だけど、日本の場合、そのへんの考え方が根本的に違うみたいですね。銀座は明治5年の大火、大正12年の関東大震災、昭和20年の空襲と、3度にわたって壊滅的な被害を受けたにもかかわらず、その度に復興してきました。でも、なかには三愛ビルのように、そういう人災や災害とは関係なしに変わっちゃう建物もたくさんあります。ということは、「変わっていく」というのが銀座とか東京の特色なんじゃないかなぁ、とも思います。 ―東京が変わっていくことは、「いいこと」でも「悪いこと」でもない、ということですか? そうだと思います。だって、人々の記憶のなかにはその街の風景が残り続けるわけだから。最近、書店に行くと、昔の街並みを写真とか絵葉書とかで再現している写真集をよく見かけるようになりましたよね。東京は変化のサイクルが早いだけに、なくなってしまった風景を記憶のなかから掘り起こす愉しみがあるとも言える。 ―そういえば、介護の現場では「回想法」といって、昔の街並みの写真を見ながら会話をすることで認知症の予防やリハビリにつなげる手法を導入している施設があるそうです。 97歳になった僕の母は、家から300~400メートル先のサービス付き高齢者向け住宅で暮らしているんだけど、血圧の薬とか飲まなきゃならないから毎朝、訪ねていくのが日課なんです。もう年相応にぼけてはいるんだけど、僕が幼稚園児や小学生だったりする頃の話をすると、元気に言葉をかえしてくれます。閉店してしまった銀座の洋食レストラン「オリンピック」の話や、実家のまわりの風景の変わり方まで、話題は豊富にあります。こういう話ができるのは、変化の激しい東京ならではですよね。 年寄りを笑ってた自分が「笑われる年寄り」になっちゃった ―2015年に泉さんは『還暦シェアハウス』(中公文庫)を出版しました。60歳の還暦を1年後に控えたフリーライターの松木を主人公にしたこの小説は、泉さんが「老い」というテーマに初めて向き合った本だと思うんですが、いかがでしょう? 僕は文章を書くとき、自分と同じ年代の人たちをつねに意識してきました。20代のときは20代の人たちに向けて、30代では30代の人たちに向けて。40歳になったときには、『新中年手帳』(幻冬舎)という本を書いています。音楽のほうでも、自分の年齢にこだわらず、普遍的なラブソングをつくり続けているユーミン(松任谷由実)みたいな人もいれば、竹内まりやさんのように子育てとかの人生経験を曲づくりに生かしている人もいますよね。僕の場合、竹内さんと同じスタイルだといえるのかもしれない。 ―『還暦シェアハウス』も、還暦前後の自分と同じ年代の人を意識して書いたものなんですね? そう。だから、必ずしも「老い」をテーマとして描こうとしていたわけではないんです。でも、結果的には「老い」のリアルな実態を描かざるを得ませんでした。同窓会とかで昔の友人と会って近況報告をすると、その半分は病院通いしている話だったり、持病の話です。『還暦シェアハウス』の冒頭で主人公が前立腺炎にかかって渋谷の泌尿器科に通うシーンから始まるのは、そのときの話から発想したんじゃないのかな。あと、主人公たちが後半で山登りをするシーンでは、糖尿病を持病に持つ同行者がインシュリン切れになって大騒ぎになるシーンもあります。最初に『街のオキテ』の話をしたけど、ネタのなかには「オシッコのシミの隠し方」なんてのがあって、20代の僕は尿漏れする年代の人をちゃかしたりしていたけど、自分自身が若いときの自分に笑われる対象になっていたわけです。 50代の老いはショックだったけど60代の老いは自然に受け入れられた ―泉さんが自身の「老い」を実感するようになったのは、何がきっかけですか? やはり、老眼でしょうね。40代後半で、職業柄、普通の人より早く来たんじゃないかと思います。徹夜で原稿を書く、なんてこともできなくなりました。ただ、年をとっても趣味の町歩きを続けたいと思って、40歳を過ぎた頃から週1でジムに通ってトレーニングを続けたおかげで、足腰の衰えを防ぐことができたのは幸いでした。それで、中高とサッカー部だった体育会魂がぶり返して、フットサルを始めたりね。若い頃、バンドを組んでいたオヤジがエレキを買い直すようなノリです。ただ、数年前、試合中にふくらはぎが肉離れを起こしたのをきっかけにフットサルはやめちゃったんだけど。 ―さすがに還暦を過ぎてフットサルというのは、ハードかもしれませんね。 自分自身の「老い」というものをふり返ってみると、50代で老眼がいよいよ進んだ頃はショックを受けたけど、60代になったときは自分の体の衰えをナイーブに考えるのではなく、自然に受け入れるような気持ちになっていたように思います。 ―『還暦シェアハウス』が明るい雰囲気の冒険小説になっているのは、60代をむかえた泉さんのそんな心境が反映されているからなのかもしれませんね。 ええ、そうですね。 「記憶をめぐる旅」は年をとればとるほどおもしろくなる ―『還暦シェアハウス』の主人公の松木は、国会図書館に行って新聞縮刷版を読むのを趣味にしていますが、これは泉さんご自身の趣味を反映しているのでしょうか? そうです。『銀ぶら百年』を書くときも、国会図書館の新聞資料室にはだいぶお世話になりました。新聞縮刷版は、仕事のために読むというより、純粋な愉しみとして読むこともよくあります。原紙やマイクロフィルムとして所蔵されているのもあるんだけど、縮刷版は年代順に並べて開架されているから、パラパラめくって読みたい記事を探しやすいんです。複写する場所がけっこう離れてて、資料室と複写カウンターとのあいだを行ったり来たりするのにけっこうな体力を要するのが玉にキズなんだけどね。 ―松木は、気まぐれにある年の縮刷版を取り出して、その時代の気分にひたることを「時代トリップ」と呼んでいますね。 年をとると、1面を飾るニュースとか社会面だけじゃなくて、スポーツ欄やテレビ番組表なんかにも目がいくようになります。思い出がたくさん蓄積されているだけに、何気ない広告ひとつで新鮮な記憶がよみがえってくることがある。こういう愉しみは、年をとることのポジティブな一面なんじゃないのかな。 ―「時代トリップ」をするには、昔の写真や新聞縮刷版以外にも方法がありますか? 日記をつけてると、だいぶいいんですけどね。僕は小学4年生のときに担任の先生から「日記をつけなさい」と言われて、中学生の頃まで毎日書いていたんだけど、子どもの頃のエピソードを思い出す資料になりますよね。あと、『銀ぶら百年』の第1回目の記事は、銀座2丁目の「銀座・伊東屋」という文具店の紹介から始めていますが、それは僕がこの店で毎年、スケジュール帳を買いに銀座散歩をしているからなんです。いちばん古いのは、1986年のもの。5年勤めた会社を辞めて、フリーのライターになって2年目の30歳のときの手帳です。 今日は、この場に持ってきてあるので開いてみましょう。えんぴつで書き入れているので、だいぶかすれていますが、1ヵ月のあいだに3つも結婚式の予定が入っている月があったりします。そんなの忘れていたけど、1986年は長女が生まれた年だから、まわりが結婚適齢期だったのは不思議ではありません。 ―お葬式の予定とかもわかるんですか? たぶん、その後の30数冊のスケジュール帳を見てみれば、書き込みしているはずです。お葬式というと、40代後半までは友だちの親が多いんだけど、50代後半になると友だち本人のお葬式に参列するようになる。日記だと、後で読むことを想定して書くから記述が具体的になりますよね。でも、スケジュール帳だと、その日に予定している行動が素っ気ない単語で書かれているだけだから、記憶の圧縮率が日記より高いんです。なかには、日記では思い出せなかったような記憶が出てくることもありますよね。 ―お葬式の話が出たところで最後に質問です。「死」は誰にも平等にやってきますが、泉さんはどのようにそのときを迎えたいですか? そういうことについては、あんまり考えたことがないなぁ。でも、やっぱり長年、馴染んだ環境で普通に死にたいですね。「子どもの頃の思い出のある実家で死にたい」と思ったところで、昔の建物がそのまま残っているわけではないし、ましてや「海を見ながら死にたい」なんて思ったりはしないでしょう。強いていえば、いつも寝ているベッドの上で静かに眠りながら死んでいくのが理想といえるでしょうか。最近、つげ義春さんの日記や漫画作品を読み返したりして、僕のなかでちょっとした「つげブーム」が起こっているんですが、初期の若い頃の作品を読んでもつげさんは「死」について、いろんなことを語っているんです。でも、ご本人は85歳を過ぎた今も、元気にご存命でしょ?こういう大先輩の存在は大きな励みになりますよね。 ―とても楽しいお話、どうもありがとうございます。 撮影/八木虎造
2023/03/24
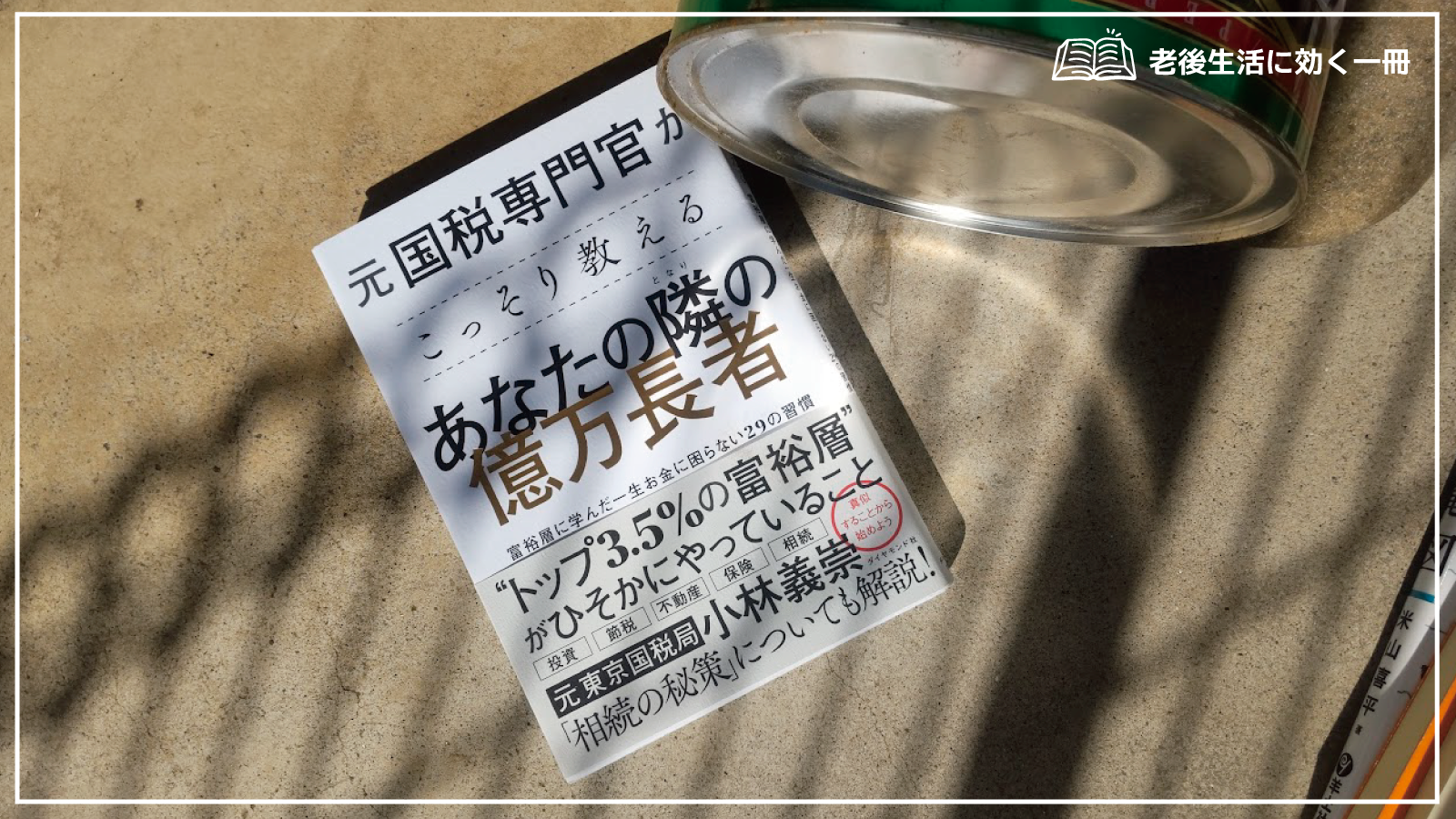
『あなたの隣の億万長者』─「あこがれの富裕層の生活の実態を知る」に効く1冊
書店の自己啓発や経済・マネーの棚を眺めていると、1冊や2冊、ともすれば3冊、4冊ほど目にする「億万長者」をタイトルにした本。 今の自分に満足しておらず、チャンスさえあればドカンと当てたいと思っている人に刺さるフレーズなのだろう。 最近では株やFX、暗号資産などの取引で資産1億円を築いた投資家を「億り人(おくりびと)」と呼ぶそうだが、そんな風潮もあって、億万長者本はちょっとしたトレンドになっている気がする。 今回紹介する本も、そうした種類の本には違いないが、興味を惹かれたのは「元国税専門官がこっそり教える」という前半のタイトルである。 著者の小林氏は、過去10年間で相続税調査などにたずさわり、2年連続で東京国税局長から功績者表彰を受けたという経歴を持つ人。それだけに、「億万長者」の実像を客観的に語ってくれるのではないかとの期待があった。その内容を紹介していこう。 『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』 著者:松永正訓 発行:ダイヤモンド社 定価:1650円(税別) ボブ的オススメ度:★★★☆☆ 「1億円超の資産を持つ人」とはどういう人か? 本書で定義される「億万長者」は、文字通り「1億円超の資産を持つ人」である。 一般的に「金持ち」と言われる人は、死亡した際、相続税を払う義務が生じるほどの資産を持つ人を指すことが多い。数100万円、あるいは1000万円くらいの資産は基礎控除の範囲内となり、課税の対象にならない。 ところが法改正によって、平成27年1月から課税対象の範囲が広がったことは記憶に新しい。 具体的には、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、相続を受けるのが妻ひとり子ひとりならば4200万円、妻ひとり子ふたりならば4800万円の資産にも相続税が発生する。 その結果として、相続税の申告対象者は全死亡者世帯の4%から8%、約2倍にまで増えたのだ。 ただ、本書の著者の小林氏が相続税調査に携わっていたのは、改正前のこと。バブル期に不動産の時価が高騰していたときの「5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)」という基準をもとにしていた時代なので、そこで出会った人たちの多くが「1億円超の資産を持つ人」だったことは間違いないだろう。 富裕層の暮らしぶりは意外にも質素だった! 小林氏がおこなっていた相続税調査とは、相続人への聞きとりをして、預金通帳や土地の権利書などに目を通して、申告内容に漏れがないかをチェックすることを言う。 本の冒頭で語られるのは、そんな人たちの意外な実状だ。引用しよう。 はじめての相続税調査で富裕層の自宅を訪問するまでは、「億万長者だから、きっと派手な生活をしているだろう」と、不謹慎ながら豪勢な生活ぶりに触れることにワクワクしていたのですが、実際に調査に入ると、その期待はあっさりと裏切られました。拍子抜けするほど、普通の暮らしぶりだったのです。 税務署内には伝統的に「相続税は最後の砦」という言葉があって、「もしこの機会にとるべき税金をとらなければ、税金を回収するチャンスは永遠に失われてしまう」との覚悟のもと、相続税申告に関する資料に目を光らすという。 資料を確認する際は、必ずその置き場に案内してもらって「現物確認」をするのだが、その間、ほかの部屋もさりげなく覗いて骨董品や金庫などの隠し財産がないか、見てまわっていたそうだ。しかし、広い家は多いものの、普通の家よりもむしろスッキリとした印象を受けることが多かったそうだ。 その後、何度も相続税調査をおこなっても、富裕層の質素な暮らしぶりに対する印象は変わることはなかったという。小林氏は、その理由について、こう分析する。 一般の人からすれば、お金はあればあるほどいいと思いがちですが、そうとは限らないのです。たとえば食費を2倍かけたからといって、人生の幸福度が2倍に高まるわけではありません。食べられる量には限りがありますし、質素な食事でも十分に満足できる人もいるでしょう。私が思うに、富裕層はお金をかけるべき物事を見極め、必要以上の食費など、効果の見込めない支出は控えています。 服装にしても、高そうなブランド品を身につけている人はほとんどおらず、ユニクロや無印良品などのようなカジュアルなファストファッション風の服装が多かったのだという。 なんだか肩すかしをくらったような気分になるが、それが「1億円超の財産を相続した人たち」の普通の姿だったのだ。 富裕層の職業には「定年」がない 相続税の申告書には、「職業」を記入する欄があって、税務職員はその情報を必ず気にしていたという。 ところが、日本の職業別平均年収トップに名をつらねる「医師」や「パイロット」などのエリート職についている人は少数派で、その多くが中小企業経営者や個人事業主だったという。 こうした人たちの共通点は、「定年がない」ことだと小林氏は指摘する。実際に小林氏は、地域に密着したマッサージ師や工務店の職人など、一見して富裕層とは結びつかない職業に就いていた人の相続税調査を少なからずおこなったという。 同じ「社長」という身分にしても、上場企業と中小企業では事情が違う。 労務行政研究所の調査によると、上場企業の社長の年間報酬は平均で約4676万円という高水準だが、上場企業のトップは「雇われ社長」が多く、短期間で交替するため、実はそれほど多くの資産を持っていない可能性があると小林氏は言う。 一方、中小企業の社長は任期が終わっても再び社長として選任されることが多く、長期にわたって報酬を受けることができます。しかも上場企業と違って、株主が親族だけでほぼ固められていることが多いので、自分の給料を自由に決められます。会社が儲かっていれば、その利益を役員報酬という形で直接懐に入れられるのです。 こうした中小企業の社長の強みは、「自社株(未公開株)」という青天井の資産を持っていることだという。なるほど、言われてみれば、至極もっともなことである。 「働いて稼ぐ」から「投資で稼ぐ」へのシフト もうひとつ、小林氏が指摘している富裕層の共通点は、「投資に熱心」だということ。 投資のリターンは、投資にかけられる元手資金に比例します。同じ年利の金融商品であれば、100万円を投資する人より、1000万円を投資する人のほうが10倍のリターンを得ることができるからです。さらに、富裕層が一般の人より投資で儲けを得やすいのは、投資手段が豊富であることも一因です。一般の人が投資できない金融商品でも、富裕層は簡単にアクセスできます。 富裕層の所得は、「働いて稼ぐ」から「投資で稼ぐ」にシフトして以降、飛躍的に増大する。 例えばスイスのプライベートバンクに口座を開設すると、「プライベートバンカー」と呼ばれる担当者が顧客の投資目標などに合わせてオーダーメイドで資産を運用してくれるという。 一般に公開されている株式ファンド(投資信託)のみならず、限定された投資家からの資金を運用するヘッジファンドや未公開株、デリバティブ(金融派生商品)などの特殊な方法を活用しながら資産を増やしてくれるのだ。 富裕層が会費数百万円の高級会員制クラブに通う理由 収入が多いことに加え、ある程度の金融知識を持っていることも富裕層の条件のひとつだ。その結果、彼らは入会金数百万円の高級会員制クラブにも惜しげなく金を使う。 高級社交クラブは限られた人しか利用できない場所ですから、利用者同士が気軽につながることができ、大きなビジネスにつなげやすくなります。このように見えない価値にもしっかりお金を使うことが、富裕層の共通点なのです。 以前、金持ち相手にプライベートジェットを販売する営業マンが会費300万円のスポーツクラブに入会して、シャワー室で「裸の営業トーク」をするという都市伝説めいた話を聞いたことがあるが、その話の信憑性が高まった気がした。 そのほかにも、本書には富裕層のさまざまな節税対策についても言及している。 「生命保険を相続税と遺産分割に活用する」「1000万円ずつ複数の口座でお金を管理する」「生活のためではなく投資のために借金する」「家族に毎年100万円のお小遣いをあげる」「富裕層は教育費に糸目をつけない」など、富裕層の人たちの資産の殖やし方が語られる。 元国税専門官という経歴を持つ人だからこそ得られた、リアルな視点である。それが、「信念を持ちなさい」とか、「毎年財布を新調しなさい」といった怪しげなアドバイスに満ちた自己啓発本と一線を画す、本書の美点だろう。
2023/03/17

【シェフ・三國清三~後編~】ぼくが37年目にして「オテル・ドゥ・ミクニ」を閉店した理由
三國清三(みくに・きよみ)シェフの自伝『三流シェフ』(幻冬舎)が話題を呼んでいる。発売から3カ月で、そろそろ10万部を突破する勢いだという。 2022年12月にシェフが「オテル・ドゥ・ミクニ」を閉店したのと同時出版という絶妙なタイミングが働いてのことだと思うが、本の内容も実に素晴らしい。 北海道の増毛という漁師町に生まれたシェフが、極貧生活のなかからたったひとつの選択肢をたぐり寄せて料理人になる道を進む、感動的なサクセスストーリーである。 『三流シェフ』には、フレディ・ジラルデ、トロワグロ兄弟、アラン・シャペルといった一流シェフの店での武者修行がイキイキと語られているが、後編のインタビューでは、帰国したシェフが「オテル・ドゥ・ミクニ」を開店したいきさつ、そして2022年12月に同店を閉店した理由について、じっくり語っていただくことにしよう。 前編もぜひご覧ください! 『三流シェフ』 著者:三國清三 発行:幻冬舎 定価:1500円(税別) 「ホテルの時代」から「オーナーシェフの時代」に ―1982年12月、ヨーロッパ修行を終えて、三國さんが28歳で日本に帰国したときの日本は、どんな状況だったのでしょう? ぼくがヨーロッパに渡る前、帝国ホテルで必死に鍋磨きをしていたころの日本のフランス料理界が「ホテルの時代」だったことはさっき言いましたよね(※前編に掲載)。ホテルに正社員として就職するというのが、一人前のフランス料理人になる唯一の道だったんです。 でも、ヨーロッパでの8年間の修行を終えて帰国したときの日本では、東京の街場のフランス料理店が脚光を浴びていました。鎌田昭男さんの「オー・シュヴァル・ブラン」、石鍋裕さんの「ビストロ・ロテュース」、井上旭さんの「ドゥ・ロアンヌ」。この3人の先輩シェフたちがブイブイ言わせていました。 そう、時代は「ホテルの時代」から「オーナーシェフの時代」に移っていたんです。村上さんの「10年経ったら君たちの時代が来ます」という予言は当たったんですね。 だから、その村上さんに帰国のあいさつに行ったとき、ホテルの仕事を紹介されても、「ありがとうございます。でも、街場のレストランで腕試しをしたいんです」と言って、お断りしました。もちろん、村上さんは「そうか。頑張れよ」と激励してくれましたよ。 ―最初は「ビストロ・サカナザ」というお店で、雇われシェフとしてスタートしたんですね? ぼくがフランスで修行していたころから「3つ星店の厨房で日本人が働いている」という噂が日本で流れていたようです。それを聞きつけたオーナーが、わざわざフランスまでやって来て「東京のビストロでシェフをやらないか」とスカウトしてくれたんです。 当時のぼくは、村上さんの言いつけを守って、収入のすべてを自己投資に費やしていましたから、貯金はゼロ。渡りに船のお誘いだったわけです。 もうひとつ、村上さんの「10年修行しなさい」という言葉もぼくは忘れていなかった。海外での修行は8年で切りあげて帰国したから、それに2年を足して、30歳になった年に自分の店を持とうと思ってました。 そうして、その決意の通りに開店したのが、「オテル・ドゥ・ミクニ」。1985年3月のことです。 開店して半年は閑古鳥。借金地獄の日々だった ―「オテル・ドゥ・ミクニ」は迎賓館赤坂離宮にほど近い住宅街に立地しています。フランス料理店と言えばアクセスのいい繁華街に開店するイメージがありますが、なぜあえてその場所を選んだのでしょう? ガヤガヤとうるさい繁華街ではなく、静かで落ちついた雰囲気の場所にあるのがヨーロッパのフランス料理店のスタンダードだったからです。 ぼくが最初に修行したフレディ・ジラルデの店は、スイスのローザンヌから車で20分のところにあるクリシエ村というところにありました。 そんな不便なところでも、予約が途切れることはありませんでした。お客さんは静かな場所で、時間を気にせず料理を楽しめる。トロワグロさんの店も、アラン・シャベルさんの店もそうでした。他に何もない田舎の村にポツンとある。 だけど、友人たちは「そんなところに店を出したらお客さんが来なくなるぞ」と口をそろえて言いました。 実際、開店して最初の半年間は、その通りになりました。開店当時、あいかわらず貯金はゼロだったから、内装も厨房設備も食器も、みんな借金して揃えたんだけど、返済するどころか毎月赤字続きで借金はどんどん膨らむばかり。もう、年をまたがずに年内で潰れてしまうだろうと頭を抱えました。 そうやって地獄のような半年が過ぎたとき、日本に「一億総グルメブーム」の風が吹いてきたんです。「グルメ」というのは本来、「美食家」「食通」と呼ばれてきた、金に糸目をつけずに食を追求するごく一部の人たちを指す言葉なんだけど、日本のバブル景気がそれを一般名詞にしたんです。 それに加えて、日本テレビの『若き天才シェフ 三國清三』というドキュメント番組が高視聴率になって、ぼくの名が知られるようになると、「オテル・ドゥ・ミクニ」は数カ月先も予約でいっぱいになる店になっていた。 ―当時、三國さんが出版した『皿の上に、僕がある。』(柴田書店)の表紙の写真を見ると、挑戦的で、尖っていた様子が感じられますね。 だって、鎌田、石鍋、井上のフレンチ三羽ガラスに対抗するには、ヒール役に徹するしかないじゃない。プロレスのザ・デストロイヤーとか、ボボ・ブラジルみたいな憎らしいヒール役。ダンディでクールな彼らのキャラクターを真似するのではなく、逆をいったわけです。案の定、見事にバズったよね(笑)。 料理のスタイルにしてもそうです。味噌も醤油も米も、平気で使ったし、天ぷらや茶碗蒸し、焼き鳥なんかの技も取り入れました。 評論家には評判が悪くて「あんなのフランス料理じゃない」「デタラメだ」なんて書かれたけど、「お前らにおれの料理がわかってたまるか」と突っぱねて、日々、お店にやって来るお客さんだけを意識して、自分のスタイルを貫いた。 そんな調子だったから、2007年にミシュランの東京版が創刊されたとき、ぼくの店には星が1個もつきませんでした。 三國シェフの30歳のときの著書『皿の上に、僕がある。』(柴田書店)。世界中のシェフの愛読書となっている。 「自分のため」より「人のため」。そのほうが限りなく頑張れるんです ―1985年3月に席数30席でオープンした「オテル・ドゥ・ミクニ」は、やがて80席のグラン・メゾンになり、世界各地の高級ホテルに呼ばれて行なったミクニ・フェスティバルも大成功。三國さんの名は「世界のミクニ」として知られるようになります。そんな三國さんは2022年12月、「オテル・ドゥ・ミクニ」を閉店して周囲を驚かせました。その背景には、何があったのでしょう? 開店から37年間、「オテル・ドゥ・ミクニ」はいろんなことを経験してきました。いいことばかりじゃありません。バブル崩壊、リーマン・ショック、3.11……といった危機にも直面したけれど、その都度、危機を乗りこえて成長してきた。 ただ、コロナの緊急事態宣言からの2か月間は、初めて「店を閉める」ということを経験したんです。 空いた時間を使って、YouTubeチャンネルを始めたりしましたけど、それと同時にこれまでのこと、これからのことをじっくり考えるきっかけにもなりました。 そうしてみると、これまでの人生でやり残してきたことがあることに気づいたんです。それは、「小さな店で、自分ひとりでお客さんと向き合い、料理を作る」ということ。 席数はカウンターのみで8席。メニューは決めない。豊洲でその日に仕入れた食材を、お客さんと相談しながら料理する。 そんな店を作りたいという思いが数年前からあって、でも、「無理だよなぁ。来世に持ち越しかもなぁ」と打ち消してきたけど、コロナ禍でそのことを考えたとき、今ならやれるかもしれない、そう思えた。 「あと3年で40周年だから、それまでやったらどうですか」というアドバイスもたくさん受けたけど、3年後のぼくは70歳になっている。そこから始めるよりも、まだまだ元気な今のうちに準備をしておきたい。 そう決めてからは、長年の立ち仕事で痛めたヒザを手術してリハビリを始めたし、我流で身につけたフランス語を基礎から学び直そうと日仏学院に通うことにしました。それから筋トレと、食事に気を遣うことで体重を70キロ台まで絞ろうとしています。マンスールといって、ダイエットとは違った方法でカロリーと栄養バランスを考え、質の高い素材と調理法で食事をするんです。 ―70歳からの再スタートをきるには、「健康であること」は必須条件なんですね。 年をとれば、人は誰だって老いていきます。プロの料理人であっても、味覚の衰えには逆らえないし、体力も減退します。だけどその一方で、「心の健康」は、自分の心がけ次第で維持していくことができます。 ―「心の健康」は、どうすれば維持できるんでしょう? いい料理店になるには、料理のクオリティを高めるだけではダメで、サービス面のホスピタリティを充実させる必要があります。クオリティとホスピタリティの両輪がなければ「いい店」はできません。 ホスピタリティとは何かというと、「お客さんに料理を楽しんでほしい」というモチベーションです。 これまで生きてきて、つくづく感じるのは「自分のため」に頑張る力には限界があるということ。どんなに頑張っても、「もうこれ以上はできない」という壁にぶち当たる。でも、自分以外の誰かのため、そう、例えば、お客さんのため、家族のため、先輩後輩や同僚のため、社会のためを考えると、人の努力は限界を超えるんです。 ぼくは、そんな努力が「心の健康」につながっているんじゃないかと思う。2024年の8月10日、ぼくは70歳になります。そのときを迎えるのが、今から楽しみ。久しぶりに充実した日々を過ごしていますよ。 ―とても楽しいお話、ありがとうございました! 撮影/八木虎造
2023/03/10
よく読まれている記事
よく読まれている記事
特集
介護の基礎知識


介護の悩みを
トータルサポート

介護施設への入居について、地域に特化した専門相談員が電話・WEB・対面などさまざまな方法でアドバイス。東証プライム上場の鎌倉新書の100%子会社である株式会社エイジプラスが運営する信頼のサービスです。

















